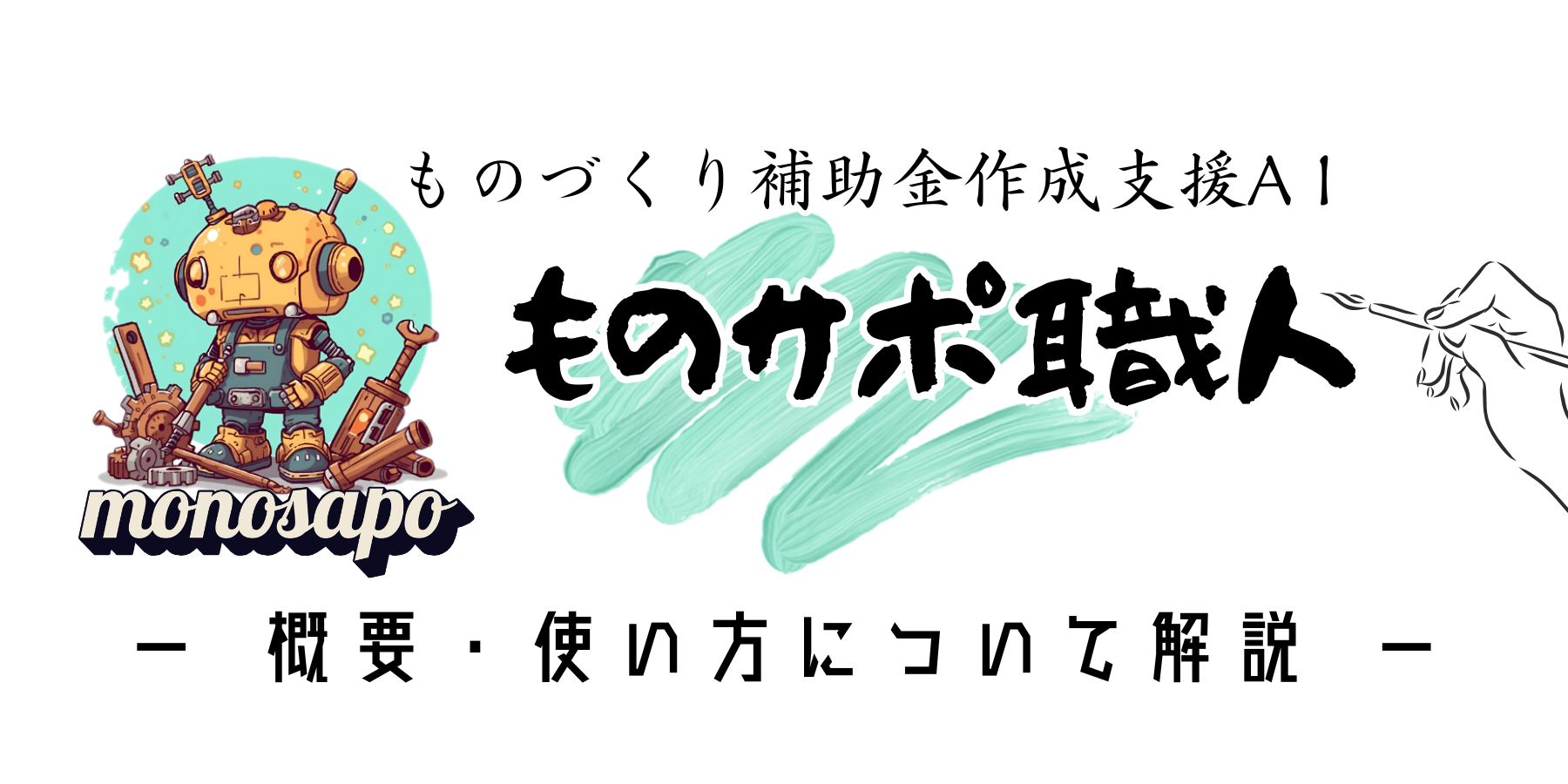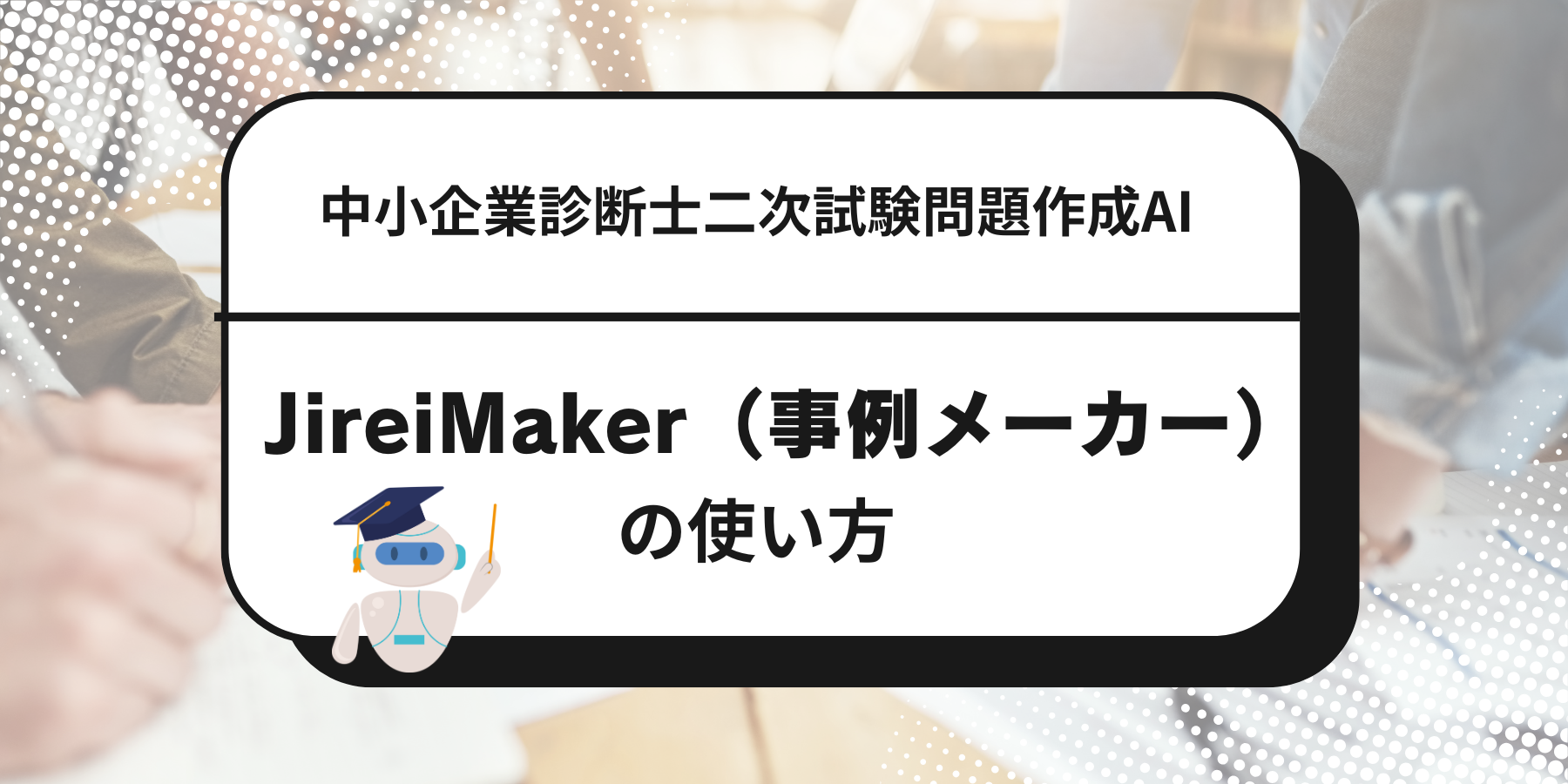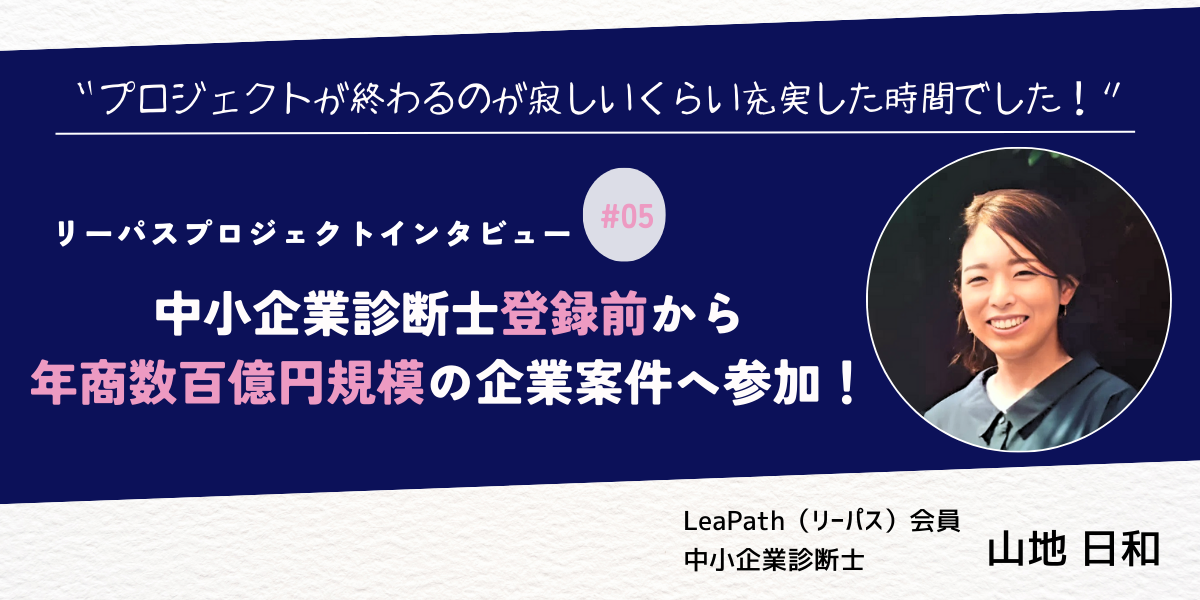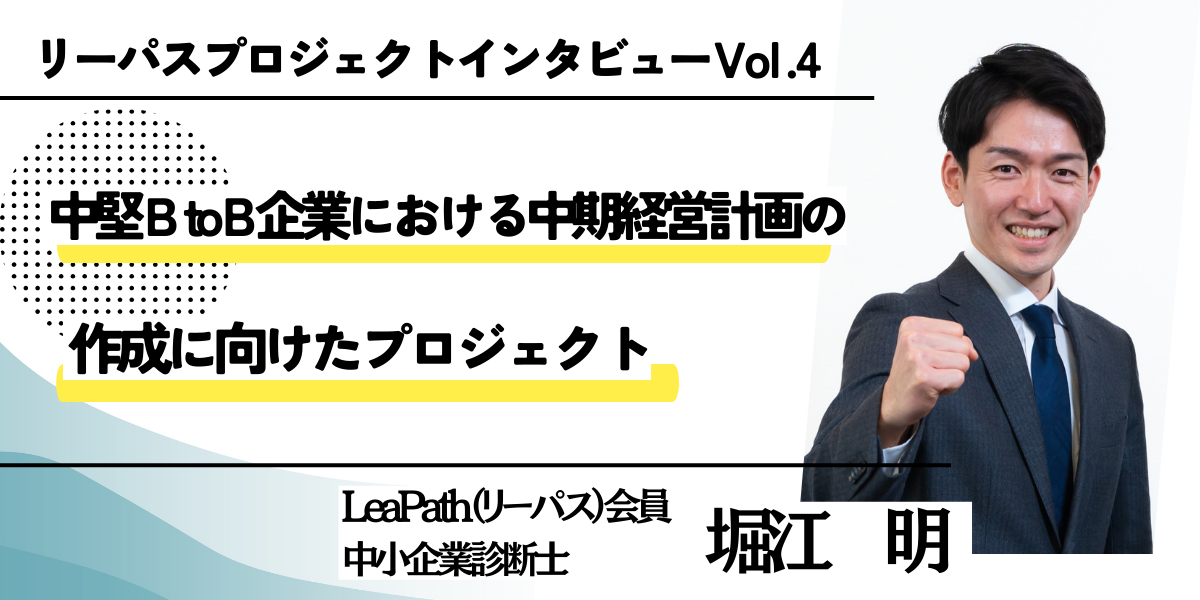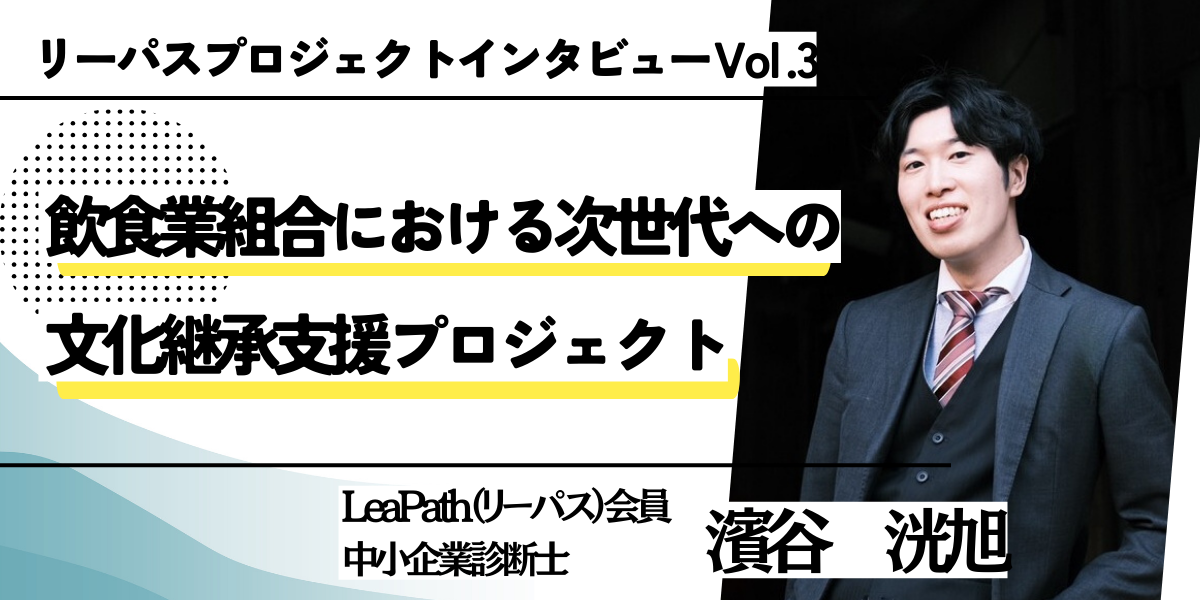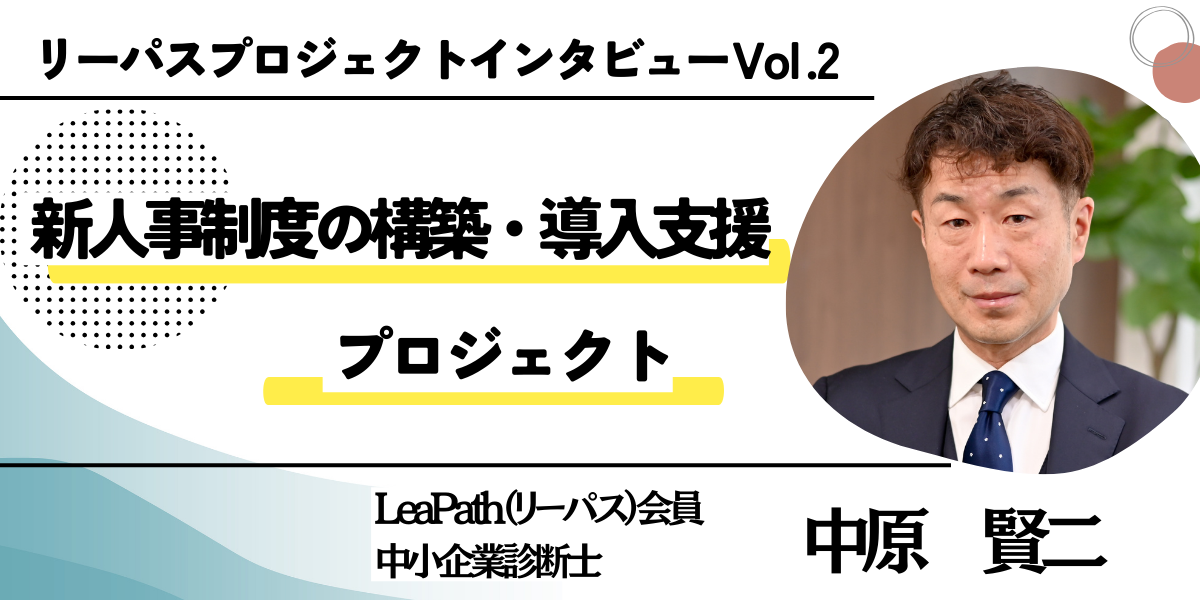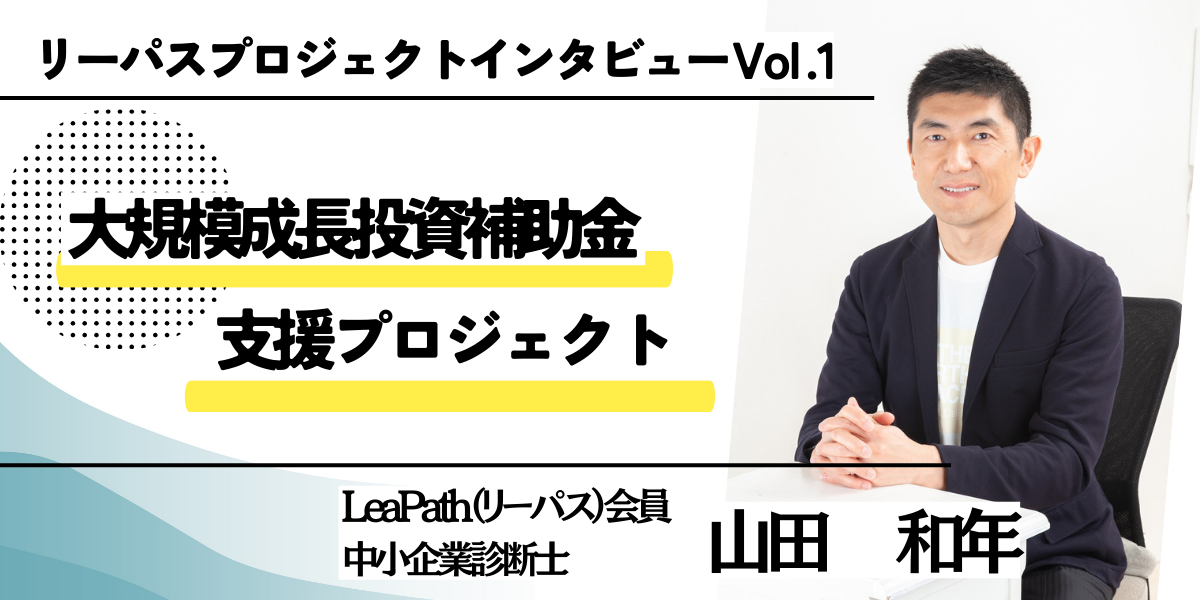今回は、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(通称:ものづくり補助金)の申請書作成支援AI ものサポ職人 の使い方を解説します。 ものサポ職人とは? ものサポ職人は、ものづくり補助金における事業計画書作成をサポートしてくれるAIツールになります。OpenAI社のChatGPT内のGPTs機能を使って作成されているため、ChatGPTのアカウント(無料登録)を持っていれば誰でも無料で利 […]
NEWS
リーパスの理念
リーパスのサービス
リーパスの強み・特徴
リーパス推薦者の声
国内最大級の診断士の超実践型プラットフォーム“リーパス”には、
賛同してくれる、力強く心強い仲間たちがいます。
賛同してくれる、力強く心強い仲間たちがいます。
リーパスの実績
2024年末のサービスリリース以降、ハイスピードで実績を積み上げています。
会員数

128名
最大単価

200万円/月
1億円以上/成果報酬
コンサル案件紹介実績数

26件
案件紹介業務提携社数

4社
顧客リピート率

約90%
プロジェクト参加診断士数

21名
コンサルティング案件紹介
リーパスでしか経験できないコンサルティング案件を紹介します。

大阪府大阪市中央区谷町1丁目(リモート)
単価:総額8万円(謝礼金6万円+議事録作成2万円)
大阪府組合への事業計画策定案件のご紹介です。
案件:人材不足解消や働き方改革等の事業計画
内容:大阪府組合との面談(最大5回・1回1時間程度)

大阪府(リモート)
単価:着手金(メイン担当者6万円/アシスタント3万円)/補助金額に対する成果報酬(メイン担当者6%)
現状、手作業で行っている大手不動産仲介サイトへの入力・更新作業を自社オリジナルのソフトウェアを開発して省力化します。社内システムへの連携機能も備えることで、まとめて一元管理できる体制を整えます。
「中小企業省力化投資補助金(補助金額500万円程度予定)」の申請支援を行う案件です。
本案件では、先方からのヒアリングを通した事業の方向性整理から申請書作成支援、事業計画作成支援など、補助金申請に関する総合的な支援をご担当いただきます。
サポート対象期間は「応募申請まで」となります。
今回は、以下の2名体制での支援を予定しています。ご応募いただく際は希望の役割についてもお知らせください。
・メイン担当者(1名):補助金申請支援の中心的な役割を担っていただきます。
・アシスタント(1名):メイン担当者の補佐を行っていただきます。補助金支援の経験は問いませんので、実務経験を積みたい方にも適したポジションです。
「中小企業省力化投資補助金(補助金額500万円程度予定)」の申請支援を行う案件です。
本案件では、先方からのヒアリングを通した事業の方向性整理から申請書作成支援、事業計画作成支援など、補助金申請に関する総合的な支援をご担当いただきます。
サポート対象期間は「応募申請まで」となります。
今回は、以下の2名体制での支援を予定しています。ご応募いただく際は希望の役割についてもお知らせください。
・メイン担当者(1名):補助金申請支援の中心的な役割を担っていただきます。
・アシスタント(1名):メイン担当者の補佐を行っていただきます。補助金支援の経験は問いませんので、実務経験を積みたい方にも適したポジションです。

大阪府大阪市北区中津
単価:総額8万円(謝礼金6万円+議事録作成2万円)
大阪府組合への事業計画策定案件のご紹介です。
案件:DX化による生産性向上(人材不足対策)を踏まえた事業計画の策定
内容:大阪府組合との面談(最大5回・1回1時間程度)

大阪 大成閣(心斎橋)
単価:24000円(税込・交通費込み)
大阪府の組合様より、創立70周年記念式典での講演講師のご依頼がありました。
「70周年にふさわしい、明るく前向きな内容」「アパレル関係の話題を含めた内容」で
20分から30分程度のご講演をお願いいたします。ご応募お待ちしております!
【今後の流れ】
1.応募者の選定
2.組合事務局ご担当者との打ち合わせ(1回)
3.本番

兵庫(基本リモートだが、要所にて現地訪問可能性あり)(リモート)
単価:着手金(メイン担当者6万円/アシスタント3万円)/補助金額に対する成果報酬(メイン担当者6%)
新事業の実施に際しての新設備の導入に対して活用する「新事業進出補助金またはものづくり補助金(補助金額400〜2500万円程度予定)」申請支援を行う案件です。
本案件では、先方からのヒアリングを通した事業の方向性整理から申請書作成支援、必要に応じた事業計画のブラッシュアップなど、補助金申請に関する総合的な支援をご担当いただきます。
サポート対象期間は「交付決定まで」となります。
今回は、以下の2名体制での支援を予定しています。ご応募いただく際は希望の役割についてもお知らせください。また、ご応募に際してリーパスでのコンサルタントプロフィールの公開をお願いしております。
・メイン担当者(1名):補助金申請支援の中心的な役割を担っていただきます。
・アシスタント(1名):メイン担当者の補佐を行っていただきます。補助金支援の経験は問いませんので、実務経験を積みたい方にも適したポジションです。
本案件では、先方からのヒアリングを通した事業の方向性整理から申請書作成支援、必要に応じた事業計画のブラッシュアップなど、補助金申請に関する総合的な支援をご担当いただきます。
サポート対象期間は「交付決定まで」となります。
今回は、以下の2名体制での支援を予定しています。ご応募いただく際は希望の役割についてもお知らせください。また、ご応募に際してリーパスでのコンサルタントプロフィールの公開をお願いしております。
・メイン担当者(1名):補助金申請支援の中心的な役割を担っていただきます。
・アシスタント(1名):メイン担当者の補佐を行っていただきます。補助金支援の経験は問いませんので、実務経験を積みたい方にも適したポジションです。

大阪(リモート)
単価:着手金(メイン担当者6万円/アシスタント3万円)/補助金額に対する成果報酬(メイン担当者6%)
新しい社内システムの導入(現状エクセルやスプレッドシート等で管理しているものを、まとめて一元管理できる新システムの導入)に対して活用する「中小企業省力化投資補助金(補助金額1000万円程度予定)」申請支援を行う案件です。
本案件では、先方からのヒアリングを通した事業の方向性整理から申請書作成支援、必要に応じた事業計画のブラッシュアップなど、補助金申請に関する総合的な支援をご担当いただきます。
サポート対象期間は「交付決定まで」となります。
今回は、以下の2名体制での支援を予定しています。ご応募いただく際は希望の役割についてもお知らせください。
・メイン担当者(1名):補助金申請支援の中心的な役割を担っていただきます。
・アシスタント(1名):メイン担当者の補佐を行っていただきます。補助金支援の経験は問いませんので、実務経験を積みたい方にも適したポジションです。
本案件では、先方からのヒアリングを通した事業の方向性整理から申請書作成支援、必要に応じた事業計画のブラッシュアップなど、補助金申請に関する総合的な支援をご担当いただきます。
サポート対象期間は「交付決定まで」となります。
今回は、以下の2名体制での支援を予定しています。ご応募いただく際は希望の役割についてもお知らせください。
・メイン担当者(1名):補助金申請支援の中心的な役割を担っていただきます。
・アシスタント(1名):メイン担当者の補佐を行っていただきます。補助金支援の経験は問いませんので、実務経験を積みたい方にも適したポジションです。

兵庫(月1回程度現地訪問可能性有り)(リモート)
単価:着手金(メイン担当者6万円/アシスタント3万円)/補助金額に対する成果報酬(メイン担当者6%)
中小企業が新たに取り組む事業に対して活用する「新事業進出補助金(補助金額2,500万円予定)」申請支援を行う案件です。
本案件では、先方からのヒアリングを通した事業の方向性整理から申請書作成支援、必要に応じた事業計画のブラッシュアップなど、補助金申請に関する総合的な支援をご担当いただきます。
今回は、以下の2名体制での支援を予定しています。ご応募いただく際は希望の役割についてもお知らせください。
・メイン担当者(1名):補助金申請支援の中心的な役割を担っていただきます。
・アシスタント(1名):メイン担当者の補佐を行っていただきます。補助金支援の経験は問いませんので、実務経験を積みたい方にも適したポジションです。
本案件では、先方からのヒアリングを通した事業の方向性整理から申請書作成支援、必要に応じた事業計画のブラッシュアップなど、補助金申請に関する総合的な支援をご担当いただきます。
今回は、以下の2名体制での支援を予定しています。ご応募いただく際は希望の役割についてもお知らせください。
・メイン担当者(1名):補助金申請支援の中心的な役割を担っていただきます。
・アシスタント(1名):メイン担当者の補佐を行っていただきます。補助金支援の経験は問いませんので、実務経験を積みたい方にも適したポジションです。

兵庫(リモート)
単価:着手金(メイン担当者6万円/アシスタント3万円)/補助金額に対する成果報酬(メイン担当者6%)
中小企業が新たに取り組む事業に対して活用する「新事業進出補助金(補助金額2,500万円予定)」申請支援を行う案件です。
本案件では、先方からのヒアリングを通した事業の方向性整理から申請書作成支援、必要に応じた事業計画のブラッシュアップなど、補助金申請に関する総合的な支援をご担当いただきます。
今回は、以下の2名体制での支援を予定しています。ご応募いただく際は希望の役割についてもお知らせください。
・メイン担当者(1名):補助金申請支援の中心的な役割を担っていただきます。
・アシスタント(1名):メイン担当者の補佐を行っていただきます。補助金支援の経験は問いませんので、実務経験を積みたい方にも適したポジションです。
本案件では、先方からのヒアリングを通した事業の方向性整理から申請書作成支援、必要に応じた事業計画のブラッシュアップなど、補助金申請に関する総合的な支援をご担当いただきます。
今回は、以下の2名体制での支援を予定しています。ご応募いただく際は希望の役割についてもお知らせください。
・メイン担当者(1名):補助金申請支援の中心的な役割を担っていただきます。
・アシスタント(1名):メイン担当者の補佐を行っていただきます。補助金支援の経験は問いませんので、実務経験を積みたい方にも適したポジションです。

大阪
単価:(A)補助金額50万円の場合・・・定額20万円 (B)補助金額200万円の場合・・・成果報酬12%
中小衣料製造業の持続化補助金の申請支援を行う。(申請資料作成・提出)
購入物
CADソフト25万円、CAD対応ノートPC15万円、モニター2万円、板タブレット2万円、サブキーボード4.5万円、プリンター20万円、ロックミシン4万円(中古)、洗濯機21万円、アトリエのリフォーム20〜40万円

大阪(一部リモート可)(リモート)
単価:300万円×10%(稼働率)
クライアントが導入する新人事制度の定着化支援を行う。
Phase1で新人事制度の構想・導入を行ったため、Phase2はより具体的な定着化支援を行う
具体的には、目標制度伴走 / 賃金制度作成 / 管理職登用支援 / 最適配置スキーム実行支援 / 面談・評価フィードバック支援 / スキルマップ支援 / 人事制度統合システム案策定などを行う。
2025年4月から開始。
募集人数:1名

大阪(一部リモート可)
単価:35万円/月
クライアントがこれまで市場競争で勝利してきた要因 を洗い出し、情報を整理することによって、次期中期経営計画の策定と経営企画機能の強化を支援する。
★現在までの「勝ち筋」を定義し、クライアントのコアコンピタンスを明らかにしたうえで報告会を実施する。
★クライアントの代表・役員の方針を確認し、考えの差分を抽出する。
★市場情報、定量的な証拠を収集し、クライアントの顧客の内部的・外部的な強みを抽出 する
★クライアントの揺るがない「強み」と、市況に合わせて構築していかなければならない新たな「強み」を抽出する
★既存の枠組みにとらわれず、クライアントの特性や目標に合わせた独自の仕組 みを共に考え、最も効果的な事業の組み合わせや計画を明確にしていく
★次期中期経営計画に資する戦略書を最終報告書にとりまとめて報告書としてクライアントに提出する。
クライアントの契約は計5カ月間、コンサルタントとの契約は1か月ごとに更新

大阪
単価:28万円/件
2024年10月~12月にかけて新人事制度の構築をリーパスで行った。次のPhaseとして人事制度を構成する各種制度の導入準備を行う。
具体的には
2025年3月に賃金制度案 / チーフ社員登用 / 最適配置案の提案 / 目標管理導入後のヒアリングと整理
2025年6月に評価面接 / 評価フィードバック支援・スキルマップ作成
訪問回数は5カ月間で6回。
上記支援ができるリーパス会員を募集します!
コンサルタント一覧
リーパスでは業界トップクラスのコンサルタントが多数在籍しています。
士業のキャリア支援
リーパスでは、第一線で活躍している士業、ハイバリューを提供し適切な報酬を獲得している士業が、今後のキャリアに磨きをかけたい士業を育成しています。

リーパス会員は、ラインワークス上で、一流コンサルタントたちとノウハウのやり取りが無料でできます。
まずは無料会員登録。会員登録後、ラインワークスの入会方法についてご案内いたします。
まずは無料会員登録。会員登録後、ラインワークスの入会方法についてご案内いたします。

記事
【ものづくり補助金作成支援AIツール】ものサポ職人の使い方について
今回は、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(通称:ものづくり補助金)の申請書作成支援AI
ものサポ職人
の使い方を解説します。
ものサポ職人とは?
ものサポ職人は、ものづくり補助金における事業計画書作成をサポートしてくれるAIツールになります。OpenAI社のChatGPT内のGPTs機能を使って作成されているため、ChatGPTのアカウント(無料登録)を持っていれば誰でも無料で利用することが可能です。
ものサポ職人でできること
ものづくり補助金事業計画書記載項目のうち、「4.事業内容」における以下項目の内容作成。
(2)事業計画名(3)事業計画の概要(5)具体的内容(5)−①今回の事業実施の背景(5)−①-2米国の追加関税措置により受けている影響の具体的内容(5)−①-3米国の追加関税措置により影響を受けている事業の現状と課題及び今後の方向性(5)−②会社全体の事業計画(5)−③今回の事業/事業実施期間の具体的アクション(5)−④今回の事業に要する経費(5)−⑤今回の事業の革新性・差別化(5)−⑥今回の事業が事業計画期間に市場に与える効果/付加価値額の増加(5)−⑦今回の事業が事業計画期間に自身に及ぼす効果/賃金引上げ(5)−⑧地域の資源や地域経済への貢献
ものサポ職人では、申請書の上記項目ごとに流れに沿って質問に答えていくだけのため、直感的で使いやすく、経営者はもちろん、担当者や支援者など、どの立場の方であっても申請作業の大幅な効率化に繋げることが可能です。
ものサポ職人の利用方法
ものサポ職人はこちらからお使いいただけます。
ものサポ職人を使う
STEP①作成を始めるをクリック
STEP②AIからの質問に対して回答を入力していく
STEP③回答が気に入らない場合はAIに修正を求めることができます。(どういう要素を入れてほしいかなど伝えるとより意図にあった文章を作成してくれます)
おわりに
以上、ものサポ職人の概要と使い方についてお話しました。皆さんのものづくり補助金申請の業務効率改善のお役に立てましたら幸いです。なお、本ツールの公開時点(2025/9/20)ではまだ、次回第21次ものづくり補助金の申請書様式は公開されておりませんので、公開され次第本ツールにつきましても最新に合わせて更新していく予定となっています。また、「ここを改善してほしい」「こんな機能・ツールが欲しい」といったご意見もぜひお待ちしております。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
講師:

濱谷洸旭

記事
【中小企業診断士二次試験問題作成AI】JireiMaker(事例メーカー)の使い方について
今回は、中小企業診断士二次試験問題作成AI
JireiMaker(事例メーカー)
の使い方を解説します。
JireiMaker(事例メーカー)とは?
JireiMaker(事例メーカー)は、中小企業診断士二次試験の事例1〜事例4の問題を作成することができるAIツールです。
診断士二次試験の問題を何度も作成することができ、これにより、診断士二次試験の過去問をやり尽くして問題も答えも覚えてしまう、いわゆる「過去問枯れ」の問題解決を図ります。
それでは早速ですが、二次試験対策AIについて使い方を話していきます。
※JireiMaker(事例メーカー)の利用については、chatGPTのアカウントが必要になります。
JireiMaker(事例メーカー)の利用方法
JireiMaker(事例メーカー)はこちらから利用できます。
JireiMaker(事例メーカー)を使う
①作成したい事例を選択する
②ー続くーと表示されたら、「続けて」と入力
③「ファイル形式にしてください」と最後に入力することで、PDFやword形式で出力し、ダウンロードすることができます
使い方は以上となります。
JireiMaker(事例メーカー)はこちらから利用できます。
講師:

濱谷洸旭

記事
業務提携のお知らせ
【業務提携のお知らせ】
この度、リーパス運営会社の「株式会社trendPlus」(代表:濱谷洸旭)と関西最大級の社会保険労務士法人である「社会保険労務士法人 和」(代表:床田知志)と業務提携するに至りました。
これにより、「リーパス」はさらに潜在顧客とのタッチポイントを増やし、「社会保険労務士法人 和」は、リーパスの士業ネットワークを活用してあらゆるコンサルティング案件に対応できることが可能になります。
社会保険労務士法人 和 https://www.101dog.co.jp/romushi/
株式会社trendPlus https://trendplus.co.jp/
リーパス https://www.leapath.jp/
株式会社trendPlus/LeaPath代表 濱谷洸旭より
「この度、関西を代表する社会保険労務士法人である『社会保険労務士法人 和』様との業務提携が実現いたしましたこと、心より嬉しく存じます。本提携を通じ、リーパスはさらなる企業との接点拡大を図り、多様な経営課題への支援体制を一層強化してまいります。今後も士業・コンサルタントの皆さまと連携し、クライアント企業にとって真に価値あるプラットフォームの実現に努めてまいります。」
LeaPathは、士業・コンサルタントが学びながら実務経験を積める実践型プラットフォームです。中小企業診断士、税理士、社会保険労務士、弁護士など多様な専門家が集まり、チームを組んで企業支援を行うことで、より質の高いサービス提供と専門性の深化を実現しています。
講師:

濱谷洸旭

記事
業務提携のお知らせ
【業務提携のお知らせ】
この度、2025年6月30日付で、リーパス運営会社の「株式会社trendPlus」(代表:濱谷洸旭)と「兵庫県信用組合」(理事長:橋爪 秀明)は、業務提携するに至りました。 これにより、「リーパス」は、さらに潜在顧客とのタッチポイントを増やし、「兵庫県信用組合」は、リーパスの士業ネットワークを活用してあらゆるコンサルティング案件に対応できることが可能になります。
兵庫県信用組合 https://www.hyogokenshin.co.jp/
株式会社trendPlus https://trendplus.co.jp/
リーパス https://leapath.jp
株式会社trendPlus/LeaPath代表 濱谷洸旭より
「地域の企業と真摯に向き合ってきた兵庫県信用組合様と共に、より深く、より広く中小企業を支援できることを大変嬉しく思っております。LeaPathとしても、士業・コンサルタントの力を結集し、現場に寄り添った支援を行ってまいります。」
LeaPathは、士業・コンサルタントが学びながら実務経験を積める実践型プラットフォームです。中小企業診断士、税理士、社会保険労務士、弁護士など多様な専門家が集まり、チームを組んで企業支援を行うことで、より質の高いサービス提供と専門性の深化を実現しています。
講師:

濱谷洸旭

記事
【実体験】中小企業診断士登録養成課程に働きながら通うことは厳しい?
こんにちは、一般社団法人Community Boost Consulting代表理事の長谷川祐介と申します。
さて今回は、私が実際に1年間通った大阪経済大学中小企業診断士登録養成課程(第5期)(以下、「大経大養成課程」といいます。)をモデルに、働きながら養成課程に通うことについてお話ししていきたいと思います。
中小企業診断士登録養成課程とは?
中小企業診断士養成課程とは、中小企業診断士資格取得のための1つのルートであり、中小企業庁が定める基準を満たした「演習」と「実習」を修了することで、2次試験と実務補習が免除され、中小企業診断士として登録できる制度です。
養成課程に働きながら通うために検討が必要な事項
私が通った大阪経済大学養成課程の場合は、基本的に授業が平日の夜と土日にあったため、働きながら通うことは可能でしたが、
それでも後述するように、仕事との両立は非常に大変でした。
また、仕事との両立はもちろんですが、養成課程に通う上では、考慮する点が多く、私自身の経験を通して、事前に理解しておくべき検討事項について大きく以下の4点を考えています。
養成課程に通うにあたって理解しておくべき検討事項
①仕事との両立
②家庭との両立
③経済的負担
④健康管理
①仕事との両立
1.会社への理解
私は普段、滋賀県に住んでおりまして、職場も同様であるため、大阪経済大学北浜キャンパスまで通うには、約1時間30分ほどかかります。
平日の18時30分から始まる講義に間に合わせるためには、少し仕事の終了時間を早めることが必要となりました。
また、養成課程では約1ヶ月かけての診断実習が計5回行われますが、実習中の1ヶ月間は毎週1回平日に実習先の会社に訪問するため、5回の実習全体を通して計16日間は、平日有休をとって出席する必要がありました。
(実習については、別記事「中小企業診断士登録養成課程の実習内容について卒業生が解説」をご参照ください。)
これらを考慮すると、職場の理解を得ることなしには、仕事との両立は難しいですので、養成課程を検討される場合は、入学前に、入念に職場と協議いただくことをお勧めします。
2.働きながら通える養成課程の選定
また、私が通った大阪経済大学の養成課程では平日夜と土日が基本となる開講日でしたので、公務員で平日フルで働いている私も通うことができましたが、
養成課程の各学校毎で開講スケジュールは変わってきますので、働きながら通いたい方は、事前に今の勤務形態で働きながら通えるかどうかをしっかり前提として検討しておくことが必要となります。
②家庭との両立
仕事の理解を得ることもさることながら、人によっては、家庭の理解を得る方が難しい方もいらっしゃるかもしれません。
週3〜4日(平日夜2日、休日日中1〜2日)通学し、家では課題のレポート作成等を、本業の仕事をしながら行うわけですから、家庭には迷惑をかけることになります。
特に、小さい子供がいらっしゃる受講生の中には、子供との距離ができてしまった等の声があがっていました。
家庭については、事前協議でどうこうなるものではないかもしれませんので、たまにあるお休みの日は全力で家族との時間に使い、家族サービスを念頭におきながら1年過ごすことが大切かと思います。
③経済的負担
また、もちろん養成課程ルートでは、2次試験ルートと比べて大きく費用がかかります。実際には私は1年間で以下の費用がかかりました。
私が養成課程で1年間にかかった費用
・(大阪経済大学)養成課程学費:200万円
・交通費:約15万円
・合計:約215万円
私は、公務員なので対象外でしたが、「専門実践教育訓練給付金」を活用できれば、約40万円国から支援を受けることができます。
しかし、それでも車が買えるくらいの費用が必要となりますので、家計との事前相談は必須です。
④健康管理
仕事と両立しながら週4回通学するとなると、健康管理はとても重要です。
養成課程を卒業する上で何より大事なのは出席率です。どれだけ良い成績を収めたとしても出席率90%の必須条件を満たせなければ卒業が認められません。
原則としてオンラインでの出席は認められていないため、病気で休みがちとなった場合は卒業できなくなる可能性があります。そのため、有休を活用し、戦略的に休養を取ることも重要となります。
養成課程通学中の一週間のスケジュール
私が実際に1年間大経大養成課程に通っていた時の1週間と1日の流れは以下の通りです。
実際にどのくらいの時間を養成課程に当てる必要があるのかをイメージいただければと思います。
<1週間のスケジュール>
月曜日 演習(18時30分~21時30分)
火曜日 自宅にてレポート+予習作業(約2〜4時間)
水曜日 演習(18時30分~21時30分)
木曜日 オフ
金曜日 自宅にてレポート+予習作業(約2〜4時間)
土曜日 演習(9時~17時45分)
日曜日 演習(9時~17時45分)
<平日(開講日)の1日のスケジュール>
授業外での作業ついて
養成課程では、講師の授業をひたすら聞き続けるような授業はほとんどなく、インプット→事例検討(グループワーク)→発表、その後、発表内容をレポート課題として作成というケースが多いです。
そのため、授業がない日でも、課題作成や授業での発表準備、授業の予習などで時間は取られてきます。
仕事の繁忙期と重なると、木・金に東京出張が入り、新幹線の中で、実習の宿題やレポート作成に勤しむこともありましたが、そのあたりは、溢れんばかりの情熱と根性で1年間乗り切りました。
まとめ
今回は、1年間働きながら中小企業診断士登録養成課程に通うという経験から、仕事との両立の厳しさをお伝えしました。最近、中小企業診断士が注目を集めている影響で、登録養成課程への入学は難しくなってきていますが、そこからの卒業もまた大変な挑戦となります。
ただ、私でやれたのですから、この記事を読んでいただいている熱心な読者の皆様には可能だと信じております。その過程で得る貴重な知識や経験、そして人脈は何物にも代え難いものです。
実際に、養成課程では、診断士二次試験対策で中心となる、読む・考える・書く能力に留まらず、ファシリテーション能力、傾聴能力、プレゼンテーション能力、ロジカルシンキング能力など、実際の実務に即した能力強化を図ることができます。
ぜひ、皆様も前向きな気持ちで養成課程への参加について検討してみてください。
講師:

長谷川祐介

記事
【社会保険労務士法人和】床田代表のインタビュー動画公開!
2024年より、LeaPathは社会保険労務士法人和と業務提携を締結しております。このたび、社会保険労務士法人和の床田代表に、LeaPathの提供する価値についてお話しいただきました。
床田代表は、社労士法人と中小企業診断士団体が連携することにより、お客様にとってより包括的かつより高いレベルの支援が可能になる点に、大きな意義があると語っていただきました。
詳しくは、ぜひ動画をご覧ください。
講師:

床田知志

記事
リーパスプロジェクトインタビューVol.5 山地日和/中堅BtoB企業における中期経営計画の作成に向けたプロジェクト
1.自己紹介
リーパス
本日はリーパス会員の中小企業診断士である山地日和さんにインタビューさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。では早速ですが、まずは簡単に自己紹介をお願いいたします。
山地さん
こんにちは、モジュールコンサルティングオフィスの山地日和です。
大手から中小まで複数の事業会社の経理・人事経験を生かして、“バックオフィスから事業を加速しよう!”というサービスを行っています。管理会計導入や人事制度見直し、採用・広報、新事業立ち上げが多いです。個人事業から法人へのスタートアップから、年商十数億の中小企業まで関与させていただいています。
また、株式会社彩墨会(クリエイティブ系の書道会社)を、書家と2人代表取締役体制で経営しています。クライアントのコーポレートアイデンティティをコンサルで引き出して書に落としこみ、ロゴやコミュニケーションツールとして活用していただくBtoBビジネスモデル。こちらも中小~中堅企業の社長とお会いする仕事です。
2つの仕事と通じて、たくさんの人と事業をたのしんでいます。
2.リーパスに登録しようと思ったきっかけについて
リーパス
リーパスに登録しようと思われたきっかけは何ですか?
山地さん
中堅以上のクライアントに対するコンサル経験を持ちたいと思って、登録しました。
営業人脈が狭く、キャリアの少ない独立中小企業診断士は、どうしても中小規模の事業者さんへの関与に偏ってしまいます。早期に幅広いクライアントと出会って、顧客価値をより高めたいとおもっていました。
大手との経験豊富なコンサルファームに行ったらいいんだろうけど、年齢的にファームに採用してもらうのは難しい…。じゃあ、ファーム出身の方と仕事するのがいいのかも、と考えていたときに、恩師として尊敬している診断士の先生にリーパスのことを聞き、これだー!と登録しました。
3.リーパスで参画したプロジェクトについて
リーパス
リーパスで参画されたプロジェクトについて教えてください。
山地さん
年商数百億円のBtoB企業をクライアントとする、次期中期経営計画を策定するための前段プロジェクトに参画しました。
本プロジェクトの目的は、クライアントのこれまでの成功要因を定義し、コアコンピタンスを明らかにすること。私が担当したのは、ベンチマーク企業のKSF(Key Success Factor:重要成功要因)を特定することと、外部環境分析(政治・経済面)の2つです。
上述したとおり、企業規模・業種ともに未知の分野であり、このプロジェクトに手を挙げたのは自身にとって大きなチャレンジでもありました。
4.リーパスでのプロジェクトの感想
リーパス
リーパスでのプロジェクトのご感想についてお願いします。
山地さん
チームでの仕事が本当に楽しい。堀江さんがインタビューVol4で答えていらっしゃったように、『クライアントにとって有益なアウトプットにしようという思いが共有できている』、これがこのチームのKSFだと思います!
お二方ともファームのご経験があり、アウトプットを作っていくプロセスではわたしにとって初めての切り口や分析手法も多く、キャッチアップするのにちょっと時間がかかって申し訳なく思うことも多々。でも、『こんなロジックの組み方するのね!』とわくわくしながら吸収しています。あと、毎回お二人のパワポ資料がくると、にやにやしながら解体して、どうやって作ってるのか研究しています笑
リーダーの中川さんはコンサル手法のみならずコミュニケーション能力がとても高く、メンバーにGoodとMoreをうまく伝えてくださいます。私にとっては、信頼できるリーダー。とても良い刺激を受けています!
5.リーパスでのプロジェクトで、必要なスキルについて
リーパス
今回のリーパスでのプロジェクトで、必要なスキルはどんなスキルでしたか?
山地さん
チームコミュニケーション力。チームメンバーそれぞれが独立しているので、日常はオフラインでのやりとりがなく顔や様子はわかりません。クライアントにいい提案しようね!という思いを軸に、信頼しあうことがまず不可欠だなと思います。
もちろん、コンサルタントとして必要な基本能力はあることが前提で進むプロジェクトだと思います。
・課題発見力:与えられたタスクを軸にしつつ、どんな貢献ができるか考えて自分からも提案する
・概念化能力:リサーチした情報を並べるだけでなく、本質をつかんで言語化しようとする
・迅速性:資料を速くつくるはもちろん、作業難航時に抱え込まず早期に相談する
などなどです。
6.今後の展望について
リーパス
今後の展望についてぜひお聞かせください。
山地さん
4月1日に中小企業診断士登録予定で、これまでの関与先に加えて、公的機関での海外支援業務や、研修講師へのチャレンジを始めます。
リーパスについては、このプロジェクトが終わったらさみしいなあというのがまず本音。また一緒に仕事しようと言っていただけるようがんばりたいですね!忙しくても、リーパスだったら時間こじあけます。ベーススキルを磨いて、次にご一緒するみなさまに『山地、腕あげたなー!』と思っていただけるように精進します。
7.中小企業診断士として活躍していきたい方に向けたメッセージ
リーパス
最後に、中小企業診断士として今後活躍していきたい方に向けたメッセージをお願いします。
山地さん
中小企業と同様、診断士も協業してシナジーを発揮することでお客さまへの価値を大きくできる業態だと思います!
公開されたプロジェクトに興味をもてたら、はじめの一歩でぜひ応募してみましょう。もしアサインされなくても、リーパス内でご自身の思いや顧客価値を他のメンバーと共有できるチャンスは得られるはず。あなたを待っている事業者さん、仕事仲間がきっといます。
講師:

山地 日和

記事
リーパスプロジェクトインタビューVol.4 堀江明/中堅BtoB企業における中期経営計画の作成に向けたプロジェクト
1.自己紹介
リーパス
本日はリーパス会員の中小企業診断士である堀江明さんにインタビューさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。では早速ですが、まずは簡単に自己紹介をお願いいたします。
堀江さん
初めまして、堀江明と申します。大津市役所と滋賀県庁で計15年間の行政経験を積み、さらに2022年からは自身で立ち上げた一般社団法人において中小企業の経営支援に従事しております。
2024年に滋賀県庁を退職し、民間企業へ転職。現在は地方自治体のDX支援にも携わっております。
診断士としては、年商数千万円から数億円規模の中小・小規模事業者に対し経営診断やDX支援を行っており、業種は多岐に渡りますが主にBtoC分野を中心に活動しています。
DX化の推進にあたっては、人材研修や業務フロー作成の支援を通じ、中小企業が自走できる体制づくりに注力しております。
2.リーパスに登録しようと思ったきっかけについて
リーパス
リーパスに登録しようと思われたきっかけは何ですか?
堀江さん
古巣でお世話になっていたリーパスメンバーさんから紹介を受けて登録しました。そのご縁で代表の中川さんと出会ったことが、実際にプロジェクトに参加しようと思ったきっかけです。
理由としては、中小企業診断士には研究や受注獲得を目的とする様々な集まりがありますが、その中でも特にリーパスが本格的かつ信頼できると感じたためです。
大手コンサルティング企業での経験をお持ちの中川さんが中小企業診断士の資格を取得したきっかけや、診断士のプレゼンスを高めたいという話をお聞きし、その思いに共感して何か力になれればと感じました。
3.リーパスで参画したプロジェクトについて
リーパス
リーパスで参画されたプロジェクトについて教えてください。
堀江さん
年商数百億円のBtoB企業をクライアントとする、次期中期経営計画を策定するための前段プロジェクトに参画しました。
本プロジェクトの目的は、クライアントのこれまでの成功要因を定義し、コアコンピタンスを明らかにすること。私が担当したのは、ベンチマーク企業のKSF(Key Success Factor:重要成功要因)を特定することと、外部環境分析(政治・経済面)の2つです。
上述したとおり、企業規模・業種ともに未知の分野であり、このプロジェクトに手を挙げたのは自身にとって大きなチャレンジでもありました。
4.リーパスでのプロジェクトの感想
リーパス
リーパスでのプロジェクトのご感想についてお願いします。
堀江さん
短い期間でしたが、PMの中川さんともう一人メンバーから多くのことを学ぶことができ、大変有意義な経験となりました。
実際の進め方としては、まずはベンチマーク企業のウェブサイトやIR情報を確認し、KSFの仮説をつくる。それらの仮説を財務情報と照らし合わせ、裏付けが可能と思われる仮説を3つほど中川さんに確認いただきました。
中川さんからは、仮説を横に広げるための視点や縦に掘り下げるための視点を丁寧に教えていただき、成果物の品質を上げるために奮闘しました。ここで学んだ思考の軸は、今後の経営支援にも活かせると考えています。
5.リーパスでのプロジェクトで、必要なスキルについて
リーパス
今回のリーパスでのプロジェクトで、必要なスキルはどんなスキルでしたか?
堀江さん
今回のような未知の分野で大事なことは、「質問力」だと思います。
一人で悩んでいても良い答えは出せないので、PMやメンバーに素早く相談する。
相談に当たっては、何に悩んでいるか、なぜ悩んでいるかを正確に伝える。そこで必要なのが、何かしらの仮説をもって質問する「質問力」だと思います。
仮説構築に当たっては、診断士として培ってきた様々なフレームワークが役に立ちました。バリューチェーン、競争戦略、5Fなど、診断士の共通言語をベースに質問するとコミュニケーションが円滑になります。そのため、悩んだら基本に立ち返るのが良いと思います。
6.今後の展望について
リーパス
今後の展望についてぜひお聞かせください。
堀江さん
これまでは、業績の厳しい中小企業や小規模事業者の方を支援することが多かったのですが、今回、中堅企業のプロジェクトに携わったことで視野が広がりました。
個人で診断士活動を行っていても、中堅企業から受注いただくことは稀であるため、今後もリーパスのプロジェクトで自身が力になれそうな案件があれば積極的に参画したいと思います。そして、それら中堅企業でのプロジェクト経験を通じてさらに成長し、滋賀県の中小企業や小規模事業者への支援に還元したいと考えています。
7.中小企業診断士として活躍していきたい方に向けたメッセージ
リーパス
最後に、中小企業診断士として今後活躍していきたい方に向けたメッセージをお願いします。
堀江さん
リーパスでは多様な案件が取り扱われているため、ぜひ積極的に応募していただくことをお勧めします。応募に際しては「未知の分野だから」や「求められるスキルが高そうだから」といった不安を抱かれるかもしれません。
しかし、今回のプロジェクト参画を通じ、応募者のスキルセットが十分に評価され、適切なメンバー構成や担当業務の割り当てが行われていることを実感いたしました。ぜひ一歩踏み出し、共にチャレンジしていきましょう。
講師:

堀江 明

記事
リーパスプロジェクトインタビュー Vol.3:飲食業組合における次世代に向けた施策立案 濱谷洸旭
1.自己紹介
リーパス
本日はリーパス会員の中小企業診断士である濱谷洸旭さんにインタビューさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。では早速ですが、まずは簡単に自己紹介をお願いいたします。
濱谷さん
初めまして、株式会社trendPlus代表/中小企業診断士の濱谷洸旭と申します。
私は新卒で入社した金融機関を8年程前に退職し、元々知識のあったWebマーケティングおよび広告事業を立ち上げました。立ち上げ後、運にも恵まれて好調で、法人化にも至りましたが、2020年に始まった新型コロナウイルスの流行に伴い、多くの企業で広告費の削減が進んだことを受けて弊社も影響を受けました。
その結果Webマーケティング領域にとどまらず、経営者や企業が抱えるさまざまな課題に対して幅広いソリューションを提供していくこと、いわゆる業務幅を広げることが必要と考えました。そこでさらにより多角的な面から経営をサポートするため中小企業診断士の資格を取得し、現在はWebマーケティングに加え、総合的な経営コンサルティングサービスを展開しています。
2.リーパスに登録しようと思ったきっかけについて
リーパス
リーパスに登録しようと思われたきっかけは何ですか?
濱谷さん
私は現在、リーパスの運営としてWebマーケティング全般に従事していますので、この立場から考えるリーパス登録のメリットについてお話ししたいと思います。
リーパスでは比較的小規模な案件から大規模な案件まで、そして業務も業種も多岐に渡ってお仕事が紹介されています。今回私が携わったお仕事では2人1組で携わりましたが、今回のように必要に応じてチーム体制でお仕事に当たることで、各々の強みを活かしてクライアントにより大きな価値提供ができる仕組みとなっていることは大きなメリットです。
というのも診断士は通常一人で仕事をする機会が多く、複数でチームを組んでお仕事にあたることで知識や経験、スキルを共有できる機会は貴重であるためです。また、チームを組んであたることで1人では対応できない規模の大きい案件にチャレンジしていくことも可能です。登録も無料となっていますので、リーパスの理念に共感いただき、コンサルタント、診断士だけでなく士業としてのキャリアをより高めていきたいと考える方はぜひご登録をお待ちしています。
3.リーパスで参画したプロジェクトについて
リーパス
リーパスで参画されたプロジェクトについて教えてください。
濱谷さん
比較的規模の大きい飲食業の協同組合様からの、これまでの当業界における飲食文化を次世代へと繋げていくための施策に関するご依頼でした。今後業界のさらなる発展に繋げるためのターゲットとすべき顧客層を定め、これまで組合様として取り組まれてきたことと現状を踏まえて、新たな施策を立案していくという内容になります。
4.リーパスでのプロジェクトの感想
リーパス
リーパスでのプロジェクトのご感想についてお願いします。
濱谷さん
適切なチームを組んでお仕事に当たることで、提案する内容をより深く練ることができ、結果としてクライアントにも大変喜んでいただき、こちらのご提案に対してすぐに取り掛かっていただけたのがコンサル冥利に尽き、嬉しかったです。1人ではここまで喜んでいただけなかったと感じており、チームを組んで当たることができたリーパスのプロジェクトならではだと感じました。
5.リーパスでのプロジェクトで、必要なスキルについて
リーパス
今回のリーパスでのプロジェクトで、必要なスキルはどんなスキルでしたか?
濱谷さん
やはり傾聴力・共感力は重要だと思います。先方の想いを聞いて、相手の立場に立って物事を考えることで初めて、相手に受け入れてもらう提案ができるスタートラインに立てるかなと思います。仮にコンサルタントとして特別なスキルや専門的な知識を持っていたとしても、社長やそこで働く方々の想いを無視した提案では受け入れてもらえません。傾聴力・共感力に関しては案件規模に限らず共通して必要となるスキルだと考えます。
6.今後の展望について
リーパス
今後の展望についてぜひお聞かせください。
濱谷さん
個人としては、現状の得意分野や規模に限らず、新たな分野、業種、規模の案件にも積極的にチャレンジしていきたいと考えています。また、経営コンサルにおけるPM経験をさらに増やしていくことで、さらに広い視点からコンサルに関わっていきたいと考えています。ジェネラリストとしての能力を高めたい一方で、最近はAI分野にも夢中なので、もっとこの辺りの分野も深く極めていきたいですね。
リーパスとしては、これまで中小企業診断士はもちろん他士業の業界がなかなか関わってこれなかった中堅企業領域へのコンサルにも進出し、いわゆるこの業界におけるパラダイムシフトを起こし、業界全体を盛り上げていきたいと考えています。
7.中小企業診断士として活躍していきたい方に向けたメッセージ
リーパス
最後に、中小企業診断士として今後活躍していきたい方に向けたメッセージをお願いします。
濱谷さん
リーパスでは会員登録が無料の上、比較的小規模な案件から大規模な案件まで、そして業務も業種も多岐に渡ってお仕事が紹介されています。
また、診断士をはじめとした士業やコンサル向けの動画や記事といった学べるコンテンツも豊富にあり、会員同士で意見・情報交換できるコミュニティもあるので、コンサルとして稼いでいきたいと考える人はもちろん、コンサルとしての知識やスキルを向上させたい方や繋がりを広げたい方にもぜひオススメです。
講師:

濱谷洸旭

記事
現役診断士が解説!中小企業診断士の独立は失敗しやすいのか?
中小企業診断士でLeaPath初期メンバーの山田です。
今回は、「現役診断士が解説!中小企業診断士の独立は失敗しやすいのか?」と題してお送りします。
私は中小企業診断士に登録したその年に独立をしました。それまでは中堅企業でのサラリーマンとして20年以上生活してきましたが、違う世界に足を踏み入れたことになります。
今回は自らの経験に加え、周りの現役診断士数名のお話を総合しながら、はたして独立すると失敗してしまうものなのかを検証してみたいと思います。
結論:中小企業診断士の独立は決して失敗しやすくない
結論から申しますと、「中小企業診断士の独立は失敗しやすいのか?」という問いに対しては「NO」と回答します。
私もここまで順調に進めてきていることもありますが、周囲を見回しても、診断士での独立が失敗しやすいという事例や悩みは聞いたことがありません。
それぞれ生きてきた環境の違いや経験値の差、また独立後の生活についての解釈の違いがあるとは思いますが、私が知る限りの解釈で以下深掘りしていきましょう。
独立診断士としての「生き方」
皆さんもご存じのとおり、中小企業診断士の活躍の場は独立だけではなく、企業内診断士、公的機関勤務、金融機関勤務、コンサルティング会社勤務など、様々なタイプがあります。各自の強みや志向に合わせて、柔軟なキャリア選択が可能な点も中小企業診断士の魅力と言えますね。
独立診断士の数と傾向
中小企業診断協会のアンケートによりますと、診断協会の会員診断士の約48%が独立診断士との情報があり、その割合は増加傾向にあると聞きます。
選択肢
回答数
構成比(%)
中小企業診断士として独立している
904
47.8
2年以内に独立したい
140
7.4
5年以内に独立したい
161
8.5
10年以内に独立したい
142
7.5
予定はない
515
27.2
無回答
30
1.6
回答数計
1,892
100.0
(出典:企業診断ニュース別冊 2023年2月)
中小企業診断士の年齢のボリュームゾーンは50代、60代、40代となっており、ある程度経験を積んだベテランであることが垣間見えますが、最近では30代の若手独立も増加しており、IT、Webマーケティングなど、新分野での活躍も目立ちます。
独立診断士の年収
コンサルティング業務日数の合計が100日以上(つまりほぼプロコン)の方にとったアンケートがあります。
選択肢
回答数
構成比(%)
300万円以内
83
14.3
301~400万円
51
8.8
401~500万円
58
10.0
501~800万円
124
21.4
801~1000万円
66
11.4
1001~1500万円
89
15.4
1501~2000万円
39
6.7
2001~2500万円
25
4.3
2501~3000万円
16
2.8
3001万円以上
28
4.8
合計
579
100.0
(出典:企業診断ニュース別冊 2023年2月)
独立診断士の年収は個人差が大きいことは否めず、経験や専門性によって変動します。
一般的には、初年度から3年目は300万円〜500万円、4年目以降は500万円〜800万円、ベテランになると800万円以上というイメージが多いのではないでしょうか?(筆者調べ)。
トップクラスでは2000万円を超える例も多くあり、また期間としても開業から数年で2000万円など到達される方もいらっしゃいます。
独立中小企業診断士の実例
独立診断士の実例として、たとえば、私の知っている独立診断士の方では以下のような方々がいらっしゃいます。
① 製造業出身の50代男性。生産性向上のコンサルティングを得意としている。前職の経験を活かし、現場改善で高い評価。補助金業務にも関わり、年収900万円以上。
② IT業界に転職した30代女性。創業支援やDX支援に注力。自らもプレイヤーに近い立ち位置で深く入り込み、多忙な様子。年収650万円程度か。
③ 元銀行員の50代男性。事業再生と財務改善が強み。地域金融機関との太いパイプを活用。年収1300万円程度か。
④ 元コンサルの30代男性。DX特化。専門知識で差別化を図る。「時給1万円」と自己評価。年収2000万円程度か。
⑤ 製造業出身の40代男性。10社以上の顧問を引き受け、日本全国を飛び回っている。継続的な支援を得意としており、クライアントとの信頼関係構築が上手い。年収1500万円程度か。
中小企業診断士の独立が失敗する原因
なにをもって独立の成功、失敗とするかは人それぞれだとは思いますが、ここでは、失敗の定義を
「売上(収益)が本人が想定した目標値に届かない」という風に定義させていただきます。
その前提で、中小企業診断士の独立が失敗する大きな原因として3つあると考えています。
中小企業診断士の独立が失敗する大きな原因
①独立コンセプトがあいまい
②情報が入ってこない
③経営者へのリスペクトが足りない
①独立コンセプトがあいまい
まず1つ目が「独立コンセプトが曖昧である」ということ。
言い換えると、「なぜ自分が独立したいのかはっきりしない」ということです。
「今の職場環境が嫌だから」「なんとなく自分を変えてみたい」といった内向きの理由であれば、たとえそれがきっかけであったとしても、その先に何もなければ長続きしにくいです。
解決策としては、まず自己分析を徹底的に行い、自身の強み、情熱、市場ニーズを明確にしましょう。
そして、それらを組み合わせた具体的な独立ビジョンを策定します。
「誰に、何を、どのように提供するか」を明確にし、その価値提案が市場で通用するか検証します。
明確な目的意識と独自の価値提案があれば、困難に直面しても粘り強く活動を継続できます。
②情報が入ってこない
独立が失敗する要因として2つ目は「情報不足(情報入ってこないこと)」です。
情報不足は、市場動向の把握や新規顧客獲得の障害となり得ます。
この問題を解決するには、積極的なネットワーキングが必要ですから、診断士の会合やセミナーやイベントへの出席を通じて、同業者や潜在顧客とのつながりを広げましょう。
人との繋がりでしか得られない貴重な情報というのはたくさんありますので、情報源を多様化し、常にアンテナを張ることで、ビジネスチャンスを逃さず、競争力を維持できます。
③経営者へのリスペクトが足りない
そして最後に診断士の独立の失敗原因として「経営者へのリスペクト不足」が挙げられます。
過去にこんな事例がありました。
ある製造業の会社の社長さんへ企業診断と課題解決の提案に入った際に、私としては現状の組織体制に大きな改善余地があると思い、組織体制を大きくガラッと変える改善提案を行いました。
結果としては、社長には刺さらず、社長としては一言、
社長
「もうそんなことはとっくに考えてるから、こんなプレゼン続けるんだったら寝るで。」
ということでした。
私は当時、自信満々で社長に提案資料を持って行ったつもりでしたが、このように結果としては全く思うようにはいきませんでした。
これは、私としては社長が考えて行ってきたこと(組織体制の検討を含めて)に対してリスペクトが足りなかったわけです。
社長のやってきたことの意図、今の現状に対する社長の考えに対するリスペクトを持って、ヒアリングから提案に至るまで臨んでいたらまた結果は変わったことでしょう。
以前、私が信頼する診断士の方にこう教えていただきました。
「相手の考えを否定することは非常に気を払うべきことであり、正論を言うことが必ずしも社長にとって良い提案になるわけではない」
この考えは私自身とても大切にしている考え方です。
このように、経営者へのリスペクト不足は、信頼関係の構築を困難にし、コンサルティングの効果を低下させます。
リスペクト不足の状態では、どんなに良い提案であったとしても基本的に社長の心には刺さってくれません。
まずは経営者の立場に立って考える習慣を身につけ、経営者が直面している課題や重圧を理解し、共感する姿勢が重要です。
これに加えて、助言を行う際も、一方的な助言ではなく、対話を通じて解決策を共に見出す姿勢が大切です。
経営者の成功事例を学び、その努力と決断力を評価する視点を養うことで、より深い信頼関係を築き、効果的な経営診断が可能になります。
これさえできれば診断士の独立は失敗しない
中小企業診断士が独立するにあたって、「これはやっておいたほうが良い」と思われる要素をいくつかご紹介したいと思います。
中小企業診断士の独立でやっていきたい要素
①差別化戦略の構築
②ネットワーキングとパートナーシップ
③継続的な自己投資と学習
④多様な収入源の確保
①差別化戦略の構築
診断士として成功するには、自身の「強み」を明確にする、これが最も重要ではないかと考えます。
中小企業診断士の世界では、他の診断士と差別化することが不可欠です。
特定の業界や分野に特化したり、独自の診断技術を磨いたりすることで、クライアントに選ばれる理由を作り出せれば最高です。
そこまで尖りきらなくても、自身の経験や専門知識を活かし、ニッチな市場でクライアントに見つけていただくことも手です。差別化することによって、高単価での受注や継続的な顧客獲得が可能になります。
例えば私の場合、マスコミ業界、メディア関係の診断は強みとできます。また、決算書を深く読み込めますので、社長のお話と併せて現状をつぶさに把握できます。そして、会社の目指す目標、あるべき姿を共有することで、より社長に寄り添う診断と助言に結びつけることができます。
②ネットワーキングとパートナーシップ
独立診断士にとって、ネットワークの構築も大変重要かと考えます。特に同業者同士の関係づくりに積極的に取り組みましょう。
経験上、中小企業診断士は他の士業に比べて同業同士の接点やコミュニケーションがより深いと考えています。
セミナーや交流会への参加や共同プロジェクトの実施などを通じて、信頼関係を築いていけると良いでしょう。また、自身の「弱み」が分かっている人ならば、補完できるパートナーを見つけて協力関係を構築することで、より幅広い案件に対応できるようになります。
私の場合、養成課程で知り合った同志や先輩、先生方との定期的な触れ合いを通じて、知り合いの知り合い、といった拡げ方でネットワークを築こうとしています。
③継続的な自己投資と学習
中小企業診断士は5年毎に登録更新をする必要があり、継続的な学習が求められています。
最新の経営理論やテクノロジーのトレンドを常に把握し、自身のスキルを磨き続けることが重要です。セミナーや研修への参加や情報交換の場への出席など、様々な方法で知識を更新しましょう。また、実際の案件を通じて得た経験を体系化し、自身の知見として蓄積していくことも大切です。
私の場合、大阪府診断協会や大阪診断士会で開催されるセミナーや研修にはなるべく参加するようにしています。その他の機関で開催されているセミナーも多くチェックしています。同じテーマでも講師によって議論の運び方や結論が異なることもままあります。
④多様な収入源の確保
独立診断士の安定した経営には、できるだけ複数の収入源を確保することが重要です。
経営診断業務だけでなく、セミナー講師、執筆活動など、様々な形で収益を得る方法を模索しましょう。
そのためには自らの「稼働率」をどのように割り振るかという考え方も重要になってきます。
アウトプットとインプットの時間配分なども熟慮せねばならないポイントです。特定の案件や顧客に依存しすぎるリスクを軽減し、安定した収入を確保できるようになれば最高ですね。異なる収入源を持つことは市場の変化にも柔軟に対応できるようになるなど好循環を生み出してくれると思います。
私の場合は、「実業を伴う診断士」を目指していますので、1週間(5日)を大きく2つに割り、週2日程度は診断士としての業務、週2日は実業に就く日、残りの1日はインプットを中心に活用する日として大きく分けて考えます。曜日で分けても、お客様の都合などに左右されますので厳密には難しいですが、頭の中の稼働率イメージを持っていると、仕事が詰んだり重複したりせず、柔軟に対応できます。
中小企業診断士で独立を考えている全ての方へ
独立することへの不安や迷い
独立するということは、ある組織からの離脱を意味します。その怖さは独立を志した方でないと分からないと思います。
これまでの会社や事務所が自分と合わない、とすっきりした気持ちを持たれている方もいらっしゃるかと思いますが、そうであっても一抹の不安は残るものです。それは社会との接点をその組織を通じて行ってきたからであって、そのタガがはずれると、本当に社会人の一員でいられるのか、その点が不安になるからだと思います。
でもきっと大丈夫。独立する人は皆その経験を越えて、立派に社会にアクセスできるようになっておられます。
収入の不安定さと資金管理
独立するにあたっては、私は最低2年分の生活できる資金を貯蓄しておくべきと考えます。
つまり、仕事がゼロの状態が2年続いたとしても生きていけるという余裕が欲しいということです。リミットが少ないほど気持ちに焦りが出てきます。
1年目はとにかく挑戦。そこからさらに1シーズンチャレンジできると思えば、気持ちの好循環が生まれ、事業展開も正のスパイラルに向いていくものと考えます。
おわりに
色々話してきましたが、一言で言えば、これまでのキャリアの棚卸を行い、専門領域の方向性を決め、学びやネットワーク構築を怠らず、紹介いただいた仕事を金額の多寡にこだわらず一所懸命にこなしていけば、必ず道は拓けるということに尽きます。
これらは何も中小企業診断士の独立だけに当てはまるものではありません。逆に言えば、中小企業診断士だけが独立に失敗しやすいという理由はどこにもないということになります。謙虚に、真摯に、感謝を忘れず日々進んでいきましょう!
講師:

山田和年

記事
リーパスプロジェクトインタビュー Vol.2:新人事制度の構築・導入支援 中原賢二
1.自己紹介
リーパス
本日はリーパス会員の中小企業診断士である中原賢二さんにインタビューさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。では早速ですが、まずは簡単に自己紹介をお願いいたします。
中原さん
中小企業診断士の中原賢二です。よろしくお願いします。
私は大手食品メーカーで経営戦略および事業戦略を担当する管理職として従事していますが、副業の許可を得て、個人事業主として診断士活動をおこなっています。
関東と関西では異なる活動をしています。
関東では、行政や公的機関からの受託事業や地域金融機関との中小企業M&AおよびPMI支援を通じて、国の中小企業支援施策を推進する専門家として中小企業振興に取り組んでいます。
一方、関西では、中小企業の持続的成長や経営力・企業価値の向上を支援する経営コンサルタントとして活動し、人的資本経営に関するセミナーの講師も務めています。
2.リーパスに登録しようと思ったきっかけについて
リーパス
リーパスに登録しようと思われたきっかけは何ですか?
中原さん
「診断士として新しい景色が見たい」という思いがあります。
私は大阪で養成課程を修了し、中小企業診断士になりました。同期生たちと共に学んだ際、私たちは「診断士になるため」に学んでいたのではなく、「診断士として何をすべきか」を学ぶことに重点を置いていました。
中小企業診断士の認知度は決して高くありません。その理由は、「中小企業診断士のあるべき姿」が明確に認知されていないからだと考えています。
「社会や企業に必要とされる中小企業診断士でありたい。診断士として新しい景色を創りたい」と考えるようになったのが、リーパスに登録しようと思ったきっかけです。
3.リーパスで参画したプロジェクトについて
リーパス
リーパスで参画されたプロジェクトについて教えてください。
中原さん
新人事制度の構築・導入を支援するプロジェクトです。
このプロジェクトでは、目標管理制度、等級制度、適正配置、賃金制度といった人事制度を2年かけて段階的に導入し、経営者が望む「経営の型」を創り出します。
4.リーパスでのプロジェクトの感想
リーパス
リーパスでのプロジェクトのご感想についてお願いします。
中原さん
新たな人事制度を導入するにあたり、全社員に対して説明会を開催し、個別面談も行いました。
これらの説明会や面談を通じて、社員の期待や将来への不安、さらには社員の家族との生活についても理解することができました。
リーパスでのプロジェクトを通じて、多くの社員の人生に影響を与える責任を実感し、社員の家族も含めた幸せの一助となる機会を得ることができたと思います。この理解が社長に伝わり、人事制度を定着させるまで支援する長期的なリピート契約につながったと考えています。
5.リーパスでのプロジェクトで、必要なスキルについて
リーパス
今回のリーパスでのプロジェクトで、必要なスキルはどんなスキルでしたか?
中原さん
私が必要だと感じるのは「傾聴力」「洞察力」「構造力」です。
お客様の頭の中や心の中にある考えや想いを引き出すためには、傾聴力が欠かせません。コンサルタントが一方的に話すのではなく、お客様の考えや想いを可視化し、言語化することが大事なスタートです。
次に、お客様の課題の本質が何であるかを特定するためには、洞察力が必要です。お客様自身が課題の本質に気づいていないことも多くあります。
その後、可視化・言語化した考えや思いを、あるべき姿に向けたプランとして具体化するためには、構造力が求められます。
コンサルタントの本質は、お客様が望む姿を見抜き、ゴールへのスキームを立体的に構築することにあると私は考えています。この立体的なスキームのクオリティが、お客様のニーズを満たし、報酬を得る基準になると考えています。
6.今後の展望について
リーパス
今後の展望についてぜひお聞かせください。
中原さん
私は企業で果たすべき責務があるため、当面は現在の領域で活動を続けます。
企業内診断士と独立診断士の違いは、お客様には関係ありませんから、企業での経験・診断士の経験を蓄積し、それらを財産として独立のタイミングを待ちたいと考えています。
独立後は、中堅企業、または中堅企業を目指す中小企業の伴走支援をおこないたいと思います。
その時まで、関東では行政や公的機関、金融機関とのネットワークと信頼関係を築き、関西では経営コンサルタント・講師の実践を重ねていきます。
7.中小企業診断士として活躍していきたい方に向けたメッセージ
リーパス
最後に、中小企業診断士として今後活躍していきたい方に向けたメッセージをお願いします。
中原さん
診断士の新しい景色を一緒に創り、診断士の価値を高めていきましょう。
私は「診断士は経営のプロフェッショナル」として広く認知されなければならないと考えています。
リーパスに登録している皆さんと共に、経営のプロフェッショナルとしての歩みを楽しみにしています。
講師:

中原賢二

記事
リーパスプロジェクトインタビュー Vol1:大規模成長投資補助金支援プロジェクト 山田和年
1.自己紹介
リーパス
本日はリーパス会員の中小企業診断士である山田和年さんにインタビューさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。では早速ですが、まずは簡単に自己紹介をお願いいたします。
山田さん
はい、よろしくお願いします。
山田和年と申します。私自身、過去に関西の放送局で26年勤務してきた経歴がありますが、その間、経営戦略、財務、労務などの管理業務部門に長く携わる一方、 編成や制作といった放送局ならではの業務も経験しました。番組プロデューサーとして10年以上チームの先頭に立ち、「見えないものづくり」を一丸で行ってきました。
現在は中小企業診断士として、各種補助金に関わる業務や、企業再生に関する業務を手がけています。簿記、会計について明るく、決算書を確認しながら企業に寄り添うのが得意です。
2.リーパスに登録しようと思ったきっかけについて
リーパス
リーパスに登録しようと思われたきっかけは何ですか?
山田さん
「リーパス」が、中小企業診断士を名実共に引き上げる崇高な理念を持っていたからです。
中小企業診断士は他の士業と比べて、各々の専門領域が多彩で幅広いと感じます。だからこそ、診断士が単独で課題に向き合うよりも、タッグを組んでチームで実務することにより、幅広い企業支援、社会貢献ができると感じています。
その中で「リーパス」は、中小企業側にも診断士側にもプラスになるような理念と、実際の仕組みが設けられていると感じたので登録しました。
3.リーパスで参画したプロジェクトについて
リーパス
リーパスで参画されたプロジェクトについて教えてください。
山田さん
「中堅・中小大規模成長投資補助金」の支援業務です。
この補助金は、中堅・中小企業が持続的な賃上げを目的に、省力化等による労働生産性の向上と事業規模の拡大を図るための投資に対して補助を行うもので、規模的には大きなものでした。私はプロジェクトリーダーのもと、プロジェクトメンバーの一人として参画しました。事務局への各種問い合わせや、事業戦略の検討を行うための資料作りを行い、ローカルベンチマークなどの必要資料を用意しました。
4.リーパスでのプロジェクトの感想
リーパス
リーパスでのプロジェクトのご感想についてお願いします。
山田さん
一人ではできない仕事でした。まさに「リーパス」の意義を感じられたプロジェクトだったと思います。
数十億単位の事業計画に夢やロマンを感じ、その計画が現実のものとなる姿をイメージして気持ちも昂りました。具体的な業務進行としても、プロジェクトリーダーの適切な指示があったので大きな混乱なくスムーズに進められたと感じています。これまで携わったことのない種類や規模のプロジェクトでも、いざやってみるとなんとかなるもので、さらなる自信につながるものと感じています。
5.リーパスでのプロジェクトで、必要なスキルについて
リーパス
今回のリーパスでのプロジェクトで、必要なスキルはどんなスキルでしたか?
山田さん
今回の私の経験からすれば「挑戦心」と「想像力」だったのではないでしょうか。
未経験のプロジェクトでも一歩踏み込んでクライアントの力になりたいと思うチャレンジ精神はありました。また、結果を出してクライアントが喜ぶ姿をイメージすることが最後までやりきる原動力になっていたと思います。無論、携わるプロジェクトによって必要なスキルは変わってくると思いますが、「中小企業診断士として誰かを笑顔にする」ということが活動の原点ではないかと思います。
6.今後の展望について
リーパス
今後の展望についてぜひお聞かせください。
山田さん
「リーパス」の事業領域がどんどん拡がって、さまざまなチームで多くのプロジェクトが行われることを期待しています。
私もそれにできるだけ参画しながら、個人的には「実業の裏付けがある診断士」を目指しています。自ら「中小企業のオヤジ」になることで、経営支援業務にも一層深みが増し、共感していただける度合いが濃くなると考えるからです。何足の草鞋を履けるか分かりませんが、可能性があればあらゆる支援の仕事に関わっていきたいと考えています。
7.独立診断士に向けたメッセージ
リーパス
山田さんは独立診断士ですが、最後に、現在独立を考えている、または将来的に中小企業診断士として独立したいと考えている方に向けたメッセージをお願いします。
山田さん
診断士として独立する際には、自分の「色」を出せるかが重要になるでしょう。
しかし「経験」がなければその「色」を出しにくいのも事実です。そこで堂々巡りをしてしまいがちですが、「リーパス」はその風穴を開けてくれる素晴らしい存在になると感じます。独立診断士の皆様は、時に「リーパス」に助けられ、時に「リーパス」を助けながら、一人の診断士としても成長できるようになれば良いなと思います。一人として同じ診断士はいません。だから楽しい世界です、共に進みましょう。
講師:

山田和年

記事
【ものづくり補助金作成支援AIツール】ものサポ職人の使い方について
今回は、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(通称:ものづくり補助金)の申請書作成支援AI
ものサポ職人
の使い方を解説します。
ものサポ職人とは?
ものサポ職人は、ものづくり補助金における事業計画書作成をサポートしてくれるAIツールになります。OpenAI社のChatGPT内のGPTs機能を使って作成されているため、ChatGPTのアカウント(無料登録)を持っていれば誰でも無料で利用することが可能です。
ものサポ職人でできること
ものづくり補助金事業計画書記載項目のうち、「4.事業内容」における以下項目の内容作成。
(2)事業計画名(3)事業計画の概要(5)具体的内容(5)−①今回の事業実施の背景(5)−①-2米国の追加関税措置により受けている影響の具体的内容(5)−①-3米国の追加関税措置により影響を受けている事業の現状と課題及び今後の方向性(5)−②会社全体の事業計画(5)−③今回の事業/事業実施期間の具体的アクション(5)−④今回の事業に要する経費(5)−⑤今回の事業の革新性・差別化(5)−⑥今回の事業が事業計画期間に市場に与える効果/付加価値額の増加(5)−⑦今回の事業が事業計画期間に自身に及ぼす効果/賃金引上げ(5)−⑧地域の資源や地域経済への貢献
ものサポ職人では、申請書の上記項目ごとに流れに沿って質問に答えていくだけのため、直感的で使いやすく、経営者はもちろん、担当者や支援者など、どの立場の方であっても申請作業の大幅な効率化に繋げることが可能です。
ものサポ職人の利用方法
ものサポ職人はこちらからお使いいただけます。
ものサポ職人を使う
STEP①作成を始めるをクリック
STEP②AIからの質問に対して回答を入力していく
STEP③回答が気に入らない場合はAIに修正を求めることができます。(どういう要素を入れてほしいかなど伝えるとより意図にあった文章を作成してくれます)
おわりに
以上、ものサポ職人の概要と使い方についてお話しました。皆さんのものづくり補助金申請の業務効率改善のお役に立てましたら幸いです。なお、本ツールの公開時点(2025/9/20)ではまだ、次回第21次ものづくり補助金の申請書様式は公開されておりませんので、公開され次第本ツールにつきましても最新に合わせて更新していく予定となっています。また、「ここを改善してほしい」「こんな機能・ツールが欲しい」といったご意見もぜひお待ちしております。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
講師:

濱谷洸旭

記事
【中小企業診断士二次試験問題作成AI】JireiMaker(事例メーカー)の使い方について
今回は、中小企業診断士二次試験問題作成AI
JireiMaker(事例メーカー)
の使い方を解説します。
JireiMaker(事例メーカー)とは?
JireiMaker(事例メーカー)は、中小企業診断士二次試験の事例1〜事例4の問題を作成することができるAIツールです。
診断士二次試験の問題を何度も作成することができ、これにより、診断士二次試験の過去問をやり尽くして問題も答えも覚えてしまう、いわゆる「過去問枯れ」の問題解決を図ります。
それでは早速ですが、二次試験対策AIについて使い方を話していきます。
※JireiMaker(事例メーカー)の利用については、chatGPTのアカウントが必要になります。
JireiMaker(事例メーカー)の利用方法
JireiMaker(事例メーカー)はこちらから利用できます。
JireiMaker(事例メーカー)を使う
①作成したい事例を選択する
②ー続くーと表示されたら、「続けて」と入力
③「ファイル形式にしてください」と最後に入力することで、PDFやword形式で出力し、ダウンロードすることができます
使い方は以上となります。
JireiMaker(事例メーカー)はこちらから利用できます。
講師:

濱谷洸旭

記事
業務提携のお知らせ
【業務提携のお知らせ】
この度、リーパス運営会社の「株式会社trendPlus」(代表:濱谷洸旭)と関西最大級の社会保険労務士法人である「社会保険労務士法人 和」(代表:床田知志)と業務提携するに至りました。
これにより、「リーパス」はさらに潜在顧客とのタッチポイントを増やし、「社会保険労務士法人 和」は、リーパスの士業ネットワークを活用してあらゆるコンサルティング案件に対応できることが可能になります。
社会保険労務士法人 和 https://www.101dog.co.jp/romushi/
株式会社trendPlus https://trendplus.co.jp/
リーパス https://www.leapath.jp/
株式会社trendPlus/LeaPath代表 濱谷洸旭より
「この度、関西を代表する社会保険労務士法人である『社会保険労務士法人 和』様との業務提携が実現いたしましたこと、心より嬉しく存じます。本提携を通じ、リーパスはさらなる企業との接点拡大を図り、多様な経営課題への支援体制を一層強化してまいります。今後も士業・コンサルタントの皆さまと連携し、クライアント企業にとって真に価値あるプラットフォームの実現に努めてまいります。」
LeaPathは、士業・コンサルタントが学びながら実務経験を積める実践型プラットフォームです。中小企業診断士、税理士、社会保険労務士、弁護士など多様な専門家が集まり、チームを組んで企業支援を行うことで、より質の高いサービス提供と専門性の深化を実現しています。
講師:

濱谷洸旭

記事
業務提携のお知らせ
【業務提携のお知らせ】
この度、2025年6月30日付で、リーパス運営会社の「株式会社trendPlus」(代表:濱谷洸旭)と「兵庫県信用組合」(理事長:橋爪 秀明)は、業務提携するに至りました。 これにより、「リーパス」は、さらに潜在顧客とのタッチポイントを増やし、「兵庫県信用組合」は、リーパスの士業ネットワークを活用してあらゆるコンサルティング案件に対応できることが可能になります。
兵庫県信用組合 https://www.hyogokenshin.co.jp/
株式会社trendPlus https://trendplus.co.jp/
リーパス https://leapath.jp
株式会社trendPlus/LeaPath代表 濱谷洸旭より
「地域の企業と真摯に向き合ってきた兵庫県信用組合様と共に、より深く、より広く中小企業を支援できることを大変嬉しく思っております。LeaPathとしても、士業・コンサルタントの力を結集し、現場に寄り添った支援を行ってまいります。」
LeaPathは、士業・コンサルタントが学びながら実務経験を積める実践型プラットフォームです。中小企業診断士、税理士、社会保険労務士、弁護士など多様な専門家が集まり、チームを組んで企業支援を行うことで、より質の高いサービス提供と専門性の深化を実現しています。
講師:

濱谷洸旭

記事
【実体験】中小企業診断士登録養成課程に働きながら通うことは厳しい?
こんにちは、一般社団法人Community Boost Consulting代表理事の長谷川祐介と申します。
さて今回は、私が実際に1年間通った大阪経済大学中小企業診断士登録養成課程(第5期)(以下、「大経大養成課程」といいます。)をモデルに、働きながら養成課程に通うことについてお話ししていきたいと思います。
中小企業診断士登録養成課程とは?
中小企業診断士養成課程とは、中小企業診断士資格取得のための1つのルートであり、中小企業庁が定める基準を満たした「演習」と「実習」を修了することで、2次試験と実務補習が免除され、中小企業診断士として登録できる制度です。
養成課程に働きながら通うために検討が必要な事項
私が通った大阪経済大学養成課程の場合は、基本的に授業が平日の夜と土日にあったため、働きながら通うことは可能でしたが、
それでも後述するように、仕事との両立は非常に大変でした。
また、仕事との両立はもちろんですが、養成課程に通う上では、考慮する点が多く、私自身の経験を通して、事前に理解しておくべき検討事項について大きく以下の4点を考えています。
養成課程に通うにあたって理解しておくべき検討事項
①仕事との両立
②家庭との両立
③経済的負担
④健康管理
①仕事との両立
1.会社への理解
私は普段、滋賀県に住んでおりまして、職場も同様であるため、大阪経済大学北浜キャンパスまで通うには、約1時間30分ほどかかります。
平日の18時30分から始まる講義に間に合わせるためには、少し仕事の終了時間を早めることが必要となりました。
また、養成課程では約1ヶ月かけての診断実習が計5回行われますが、実習中の1ヶ月間は毎週1回平日に実習先の会社に訪問するため、5回の実習全体を通して計16日間は、平日有休をとって出席する必要がありました。
(実習については、別記事「中小企業診断士登録養成課程の実習内容について卒業生が解説」をご参照ください。)
これらを考慮すると、職場の理解を得ることなしには、仕事との両立は難しいですので、養成課程を検討される場合は、入学前に、入念に職場と協議いただくことをお勧めします。
2.働きながら通える養成課程の選定
また、私が通った大阪経済大学の養成課程では平日夜と土日が基本となる開講日でしたので、公務員で平日フルで働いている私も通うことができましたが、
養成課程の各学校毎で開講スケジュールは変わってきますので、働きながら通いたい方は、事前に今の勤務形態で働きながら通えるかどうかをしっかり前提として検討しておくことが必要となります。
②家庭との両立
仕事の理解を得ることもさることながら、人によっては、家庭の理解を得る方が難しい方もいらっしゃるかもしれません。
週3〜4日(平日夜2日、休日日中1〜2日)通学し、家では課題のレポート作成等を、本業の仕事をしながら行うわけですから、家庭には迷惑をかけることになります。
特に、小さい子供がいらっしゃる受講生の中には、子供との距離ができてしまった等の声があがっていました。
家庭については、事前協議でどうこうなるものではないかもしれませんので、たまにあるお休みの日は全力で家族との時間に使い、家族サービスを念頭におきながら1年過ごすことが大切かと思います。
③経済的負担
また、もちろん養成課程ルートでは、2次試験ルートと比べて大きく費用がかかります。実際には私は1年間で以下の費用がかかりました。
私が養成課程で1年間にかかった費用
・(大阪経済大学)養成課程学費:200万円
・交通費:約15万円
・合計:約215万円
私は、公務員なので対象外でしたが、「専門実践教育訓練給付金」を活用できれば、約40万円国から支援を受けることができます。
しかし、それでも車が買えるくらいの費用が必要となりますので、家計との事前相談は必須です。
④健康管理
仕事と両立しながら週4回通学するとなると、健康管理はとても重要です。
養成課程を卒業する上で何より大事なのは出席率です。どれだけ良い成績を収めたとしても出席率90%の必須条件を満たせなければ卒業が認められません。
原則としてオンラインでの出席は認められていないため、病気で休みがちとなった場合は卒業できなくなる可能性があります。そのため、有休を活用し、戦略的に休養を取ることも重要となります。
養成課程通学中の一週間のスケジュール
私が実際に1年間大経大養成課程に通っていた時の1週間と1日の流れは以下の通りです。
実際にどのくらいの時間を養成課程に当てる必要があるのかをイメージいただければと思います。
<1週間のスケジュール>
月曜日 演習(18時30分~21時30分)
火曜日 自宅にてレポート+予習作業(約2〜4時間)
水曜日 演習(18時30分~21時30分)
木曜日 オフ
金曜日 自宅にてレポート+予習作業(約2〜4時間)
土曜日 演習(9時~17時45分)
日曜日 演習(9時~17時45分)
<平日(開講日)の1日のスケジュール>
授業外での作業ついて
養成課程では、講師の授業をひたすら聞き続けるような授業はほとんどなく、インプット→事例検討(グループワーク)→発表、その後、発表内容をレポート課題として作成というケースが多いです。
そのため、授業がない日でも、課題作成や授業での発表準備、授業の予習などで時間は取られてきます。
仕事の繁忙期と重なると、木・金に東京出張が入り、新幹線の中で、実習の宿題やレポート作成に勤しむこともありましたが、そのあたりは、溢れんばかりの情熱と根性で1年間乗り切りました。
まとめ
今回は、1年間働きながら中小企業診断士登録養成課程に通うという経験から、仕事との両立の厳しさをお伝えしました。最近、中小企業診断士が注目を集めている影響で、登録養成課程への入学は難しくなってきていますが、そこからの卒業もまた大変な挑戦となります。
ただ、私でやれたのですから、この記事を読んでいただいている熱心な読者の皆様には可能だと信じております。その過程で得る貴重な知識や経験、そして人脈は何物にも代え難いものです。
実際に、養成課程では、診断士二次試験対策で中心となる、読む・考える・書く能力に留まらず、ファシリテーション能力、傾聴能力、プレゼンテーション能力、ロジカルシンキング能力など、実際の実務に即した能力強化を図ることができます。
ぜひ、皆様も前向きな気持ちで養成課程への参加について検討してみてください。
講師:

長谷川祐介

記事
【社会保険労務士法人和】床田代表のインタビュー動画公開!
2024年より、LeaPathは社会保険労務士法人和と業務提携を締結しております。このたび、社会保険労務士法人和の床田代表に、LeaPathの提供する価値についてお話しいただきました。
床田代表は、社労士法人と中小企業診断士団体が連携することにより、お客様にとってより包括的かつより高いレベルの支援が可能になる点に、大きな意義があると語っていただきました。
詳しくは、ぜひ動画をご覧ください。
講師:

床田知志

記事
リーパスプロジェクトインタビューVol.5 山地日和/中堅BtoB企業における中期経営計画の作成に向けたプロジェクト
1.自己紹介
リーパス
本日はリーパス会員の中小企業診断士である山地日和さんにインタビューさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。では早速ですが、まずは簡単に自己紹介をお願いいたします。
山地さん
こんにちは、モジュールコンサルティングオフィスの山地日和です。
大手から中小まで複数の事業会社の経理・人事経験を生かして、“バックオフィスから事業を加速しよう!”というサービスを行っています。管理会計導入や人事制度見直し、採用・広報、新事業立ち上げが多いです。個人事業から法人へのスタートアップから、年商十数億の中小企業まで関与させていただいています。
また、株式会社彩墨会(クリエイティブ系の書道会社)を、書家と2人代表取締役体制で経営しています。クライアントのコーポレートアイデンティティをコンサルで引き出して書に落としこみ、ロゴやコミュニケーションツールとして活用していただくBtoBビジネスモデル。こちらも中小~中堅企業の社長とお会いする仕事です。
2つの仕事と通じて、たくさんの人と事業をたのしんでいます。
2.リーパスに登録しようと思ったきっかけについて
リーパス
リーパスに登録しようと思われたきっかけは何ですか?
山地さん
中堅以上のクライアントに対するコンサル経験を持ちたいと思って、登録しました。
営業人脈が狭く、キャリアの少ない独立中小企業診断士は、どうしても中小規模の事業者さんへの関与に偏ってしまいます。早期に幅広いクライアントと出会って、顧客価値をより高めたいとおもっていました。
大手との経験豊富なコンサルファームに行ったらいいんだろうけど、年齢的にファームに採用してもらうのは難しい…。じゃあ、ファーム出身の方と仕事するのがいいのかも、と考えていたときに、恩師として尊敬している診断士の先生にリーパスのことを聞き、これだー!と登録しました。
3.リーパスで参画したプロジェクトについて
リーパス
リーパスで参画されたプロジェクトについて教えてください。
山地さん
年商数百億円のBtoB企業をクライアントとする、次期中期経営計画を策定するための前段プロジェクトに参画しました。
本プロジェクトの目的は、クライアントのこれまでの成功要因を定義し、コアコンピタンスを明らかにすること。私が担当したのは、ベンチマーク企業のKSF(Key Success Factor:重要成功要因)を特定することと、外部環境分析(政治・経済面)の2つです。
上述したとおり、企業規模・業種ともに未知の分野であり、このプロジェクトに手を挙げたのは自身にとって大きなチャレンジでもありました。
4.リーパスでのプロジェクトの感想
リーパス
リーパスでのプロジェクトのご感想についてお願いします。
山地さん
チームでの仕事が本当に楽しい。堀江さんがインタビューVol4で答えていらっしゃったように、『クライアントにとって有益なアウトプットにしようという思いが共有できている』、これがこのチームのKSFだと思います!
お二方ともファームのご経験があり、アウトプットを作っていくプロセスではわたしにとって初めての切り口や分析手法も多く、キャッチアップするのにちょっと時間がかかって申し訳なく思うことも多々。でも、『こんなロジックの組み方するのね!』とわくわくしながら吸収しています。あと、毎回お二人のパワポ資料がくると、にやにやしながら解体して、どうやって作ってるのか研究しています笑
リーダーの中川さんはコンサル手法のみならずコミュニケーション能力がとても高く、メンバーにGoodとMoreをうまく伝えてくださいます。私にとっては、信頼できるリーダー。とても良い刺激を受けています!
5.リーパスでのプロジェクトで、必要なスキルについて
リーパス
今回のリーパスでのプロジェクトで、必要なスキルはどんなスキルでしたか?
山地さん
チームコミュニケーション力。チームメンバーそれぞれが独立しているので、日常はオフラインでのやりとりがなく顔や様子はわかりません。クライアントにいい提案しようね!という思いを軸に、信頼しあうことがまず不可欠だなと思います。
もちろん、コンサルタントとして必要な基本能力はあることが前提で進むプロジェクトだと思います。
・課題発見力:与えられたタスクを軸にしつつ、どんな貢献ができるか考えて自分からも提案する
・概念化能力:リサーチした情報を並べるだけでなく、本質をつかんで言語化しようとする
・迅速性:資料を速くつくるはもちろん、作業難航時に抱え込まず早期に相談する
などなどです。
6.今後の展望について
リーパス
今後の展望についてぜひお聞かせください。
山地さん
4月1日に中小企業診断士登録予定で、これまでの関与先に加えて、公的機関での海外支援業務や、研修講師へのチャレンジを始めます。
リーパスについては、このプロジェクトが終わったらさみしいなあというのがまず本音。また一緒に仕事しようと言っていただけるようがんばりたいですね!忙しくても、リーパスだったら時間こじあけます。ベーススキルを磨いて、次にご一緒するみなさまに『山地、腕あげたなー!』と思っていただけるように精進します。
7.中小企業診断士として活躍していきたい方に向けたメッセージ
リーパス
最後に、中小企業診断士として今後活躍していきたい方に向けたメッセージをお願いします。
山地さん
中小企業と同様、診断士も協業してシナジーを発揮することでお客さまへの価値を大きくできる業態だと思います!
公開されたプロジェクトに興味をもてたら、はじめの一歩でぜひ応募してみましょう。もしアサインされなくても、リーパス内でご自身の思いや顧客価値を他のメンバーと共有できるチャンスは得られるはず。あなたを待っている事業者さん、仕事仲間がきっといます。
講師:

山地 日和

記事
リーパスプロジェクトインタビューVol.4 堀江明/中堅BtoB企業における中期経営計画の作成に向けたプロジェクト
1.自己紹介
リーパス
本日はリーパス会員の中小企業診断士である堀江明さんにインタビューさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。では早速ですが、まずは簡単に自己紹介をお願いいたします。
堀江さん
初めまして、堀江明と申します。大津市役所と滋賀県庁で計15年間の行政経験を積み、さらに2022年からは自身で立ち上げた一般社団法人において中小企業の経営支援に従事しております。
2024年に滋賀県庁を退職し、民間企業へ転職。現在は地方自治体のDX支援にも携わっております。
診断士としては、年商数千万円から数億円規模の中小・小規模事業者に対し経営診断やDX支援を行っており、業種は多岐に渡りますが主にBtoC分野を中心に活動しています。
DX化の推進にあたっては、人材研修や業務フロー作成の支援を通じ、中小企業が自走できる体制づくりに注力しております。
2.リーパスに登録しようと思ったきっかけについて
リーパス
リーパスに登録しようと思われたきっかけは何ですか?
堀江さん
古巣でお世話になっていたリーパスメンバーさんから紹介を受けて登録しました。そのご縁で代表の中川さんと出会ったことが、実際にプロジェクトに参加しようと思ったきっかけです。
理由としては、中小企業診断士には研究や受注獲得を目的とする様々な集まりがありますが、その中でも特にリーパスが本格的かつ信頼できると感じたためです。
大手コンサルティング企業での経験をお持ちの中川さんが中小企業診断士の資格を取得したきっかけや、診断士のプレゼンスを高めたいという話をお聞きし、その思いに共感して何か力になれればと感じました。
3.リーパスで参画したプロジェクトについて
リーパス
リーパスで参画されたプロジェクトについて教えてください。
堀江さん
年商数百億円のBtoB企業をクライアントとする、次期中期経営計画を策定するための前段プロジェクトに参画しました。
本プロジェクトの目的は、クライアントのこれまでの成功要因を定義し、コアコンピタンスを明らかにすること。私が担当したのは、ベンチマーク企業のKSF(Key Success Factor:重要成功要因)を特定することと、外部環境分析(政治・経済面)の2つです。
上述したとおり、企業規模・業種ともに未知の分野であり、このプロジェクトに手を挙げたのは自身にとって大きなチャレンジでもありました。
4.リーパスでのプロジェクトの感想
リーパス
リーパスでのプロジェクトのご感想についてお願いします。
堀江さん
短い期間でしたが、PMの中川さんともう一人メンバーから多くのことを学ぶことができ、大変有意義な経験となりました。
実際の進め方としては、まずはベンチマーク企業のウェブサイトやIR情報を確認し、KSFの仮説をつくる。それらの仮説を財務情報と照らし合わせ、裏付けが可能と思われる仮説を3つほど中川さんに確認いただきました。
中川さんからは、仮説を横に広げるための視点や縦に掘り下げるための視点を丁寧に教えていただき、成果物の品質を上げるために奮闘しました。ここで学んだ思考の軸は、今後の経営支援にも活かせると考えています。
5.リーパスでのプロジェクトで、必要なスキルについて
リーパス
今回のリーパスでのプロジェクトで、必要なスキルはどんなスキルでしたか?
堀江さん
今回のような未知の分野で大事なことは、「質問力」だと思います。
一人で悩んでいても良い答えは出せないので、PMやメンバーに素早く相談する。
相談に当たっては、何に悩んでいるか、なぜ悩んでいるかを正確に伝える。そこで必要なのが、何かしらの仮説をもって質問する「質問力」だと思います。
仮説構築に当たっては、診断士として培ってきた様々なフレームワークが役に立ちました。バリューチェーン、競争戦略、5Fなど、診断士の共通言語をベースに質問するとコミュニケーションが円滑になります。そのため、悩んだら基本に立ち返るのが良いと思います。
6.今後の展望について
リーパス
今後の展望についてぜひお聞かせください。
堀江さん
これまでは、業績の厳しい中小企業や小規模事業者の方を支援することが多かったのですが、今回、中堅企業のプロジェクトに携わったことで視野が広がりました。
個人で診断士活動を行っていても、中堅企業から受注いただくことは稀であるため、今後もリーパスのプロジェクトで自身が力になれそうな案件があれば積極的に参画したいと思います。そして、それら中堅企業でのプロジェクト経験を通じてさらに成長し、滋賀県の中小企業や小規模事業者への支援に還元したいと考えています。
7.中小企業診断士として活躍していきたい方に向けたメッセージ
リーパス
最後に、中小企業診断士として今後活躍していきたい方に向けたメッセージをお願いします。
堀江さん
リーパスでは多様な案件が取り扱われているため、ぜひ積極的に応募していただくことをお勧めします。応募に際しては「未知の分野だから」や「求められるスキルが高そうだから」といった不安を抱かれるかもしれません。
しかし、今回のプロジェクト参画を通じ、応募者のスキルセットが十分に評価され、適切なメンバー構成や担当業務の割り当てが行われていることを実感いたしました。ぜひ一歩踏み出し、共にチャレンジしていきましょう。
講師:

堀江 明

記事
リーパスプロジェクトインタビュー Vol.3:飲食業組合における次世代に向けた施策立案 濱谷洸旭
1.自己紹介
リーパス
本日はリーパス会員の中小企業診断士である濱谷洸旭さんにインタビューさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。では早速ですが、まずは簡単に自己紹介をお願いいたします。
濱谷さん
初めまして、株式会社trendPlus代表/中小企業診断士の濱谷洸旭と申します。
私は新卒で入社した金融機関を8年程前に退職し、元々知識のあったWebマーケティングおよび広告事業を立ち上げました。立ち上げ後、運にも恵まれて好調で、法人化にも至りましたが、2020年に始まった新型コロナウイルスの流行に伴い、多くの企業で広告費の削減が進んだことを受けて弊社も影響を受けました。
その結果Webマーケティング領域にとどまらず、経営者や企業が抱えるさまざまな課題に対して幅広いソリューションを提供していくこと、いわゆる業務幅を広げることが必要と考えました。そこでさらにより多角的な面から経営をサポートするため中小企業診断士の資格を取得し、現在はWebマーケティングに加え、総合的な経営コンサルティングサービスを展開しています。
2.リーパスに登録しようと思ったきっかけについて
リーパス
リーパスに登録しようと思われたきっかけは何ですか?
濱谷さん
私は現在、リーパスの運営としてWebマーケティング全般に従事していますので、この立場から考えるリーパス登録のメリットについてお話ししたいと思います。
リーパスでは比較的小規模な案件から大規模な案件まで、そして業務も業種も多岐に渡ってお仕事が紹介されています。今回私が携わったお仕事では2人1組で携わりましたが、今回のように必要に応じてチーム体制でお仕事に当たることで、各々の強みを活かしてクライアントにより大きな価値提供ができる仕組みとなっていることは大きなメリットです。
というのも診断士は通常一人で仕事をする機会が多く、複数でチームを組んでお仕事にあたることで知識や経験、スキルを共有できる機会は貴重であるためです。また、チームを組んであたることで1人では対応できない規模の大きい案件にチャレンジしていくことも可能です。登録も無料となっていますので、リーパスの理念に共感いただき、コンサルタント、診断士だけでなく士業としてのキャリアをより高めていきたいと考える方はぜひご登録をお待ちしています。
3.リーパスで参画したプロジェクトについて
リーパス
リーパスで参画されたプロジェクトについて教えてください。
濱谷さん
比較的規模の大きい飲食業の協同組合様からの、これまでの当業界における飲食文化を次世代へと繋げていくための施策に関するご依頼でした。今後業界のさらなる発展に繋げるためのターゲットとすべき顧客層を定め、これまで組合様として取り組まれてきたことと現状を踏まえて、新たな施策を立案していくという内容になります。
4.リーパスでのプロジェクトの感想
リーパス
リーパスでのプロジェクトのご感想についてお願いします。
濱谷さん
適切なチームを組んでお仕事に当たることで、提案する内容をより深く練ることができ、結果としてクライアントにも大変喜んでいただき、こちらのご提案に対してすぐに取り掛かっていただけたのがコンサル冥利に尽き、嬉しかったです。1人ではここまで喜んでいただけなかったと感じており、チームを組んで当たることができたリーパスのプロジェクトならではだと感じました。
5.リーパスでのプロジェクトで、必要なスキルについて
リーパス
今回のリーパスでのプロジェクトで、必要なスキルはどんなスキルでしたか?
濱谷さん
やはり傾聴力・共感力は重要だと思います。先方の想いを聞いて、相手の立場に立って物事を考えることで初めて、相手に受け入れてもらう提案ができるスタートラインに立てるかなと思います。仮にコンサルタントとして特別なスキルや専門的な知識を持っていたとしても、社長やそこで働く方々の想いを無視した提案では受け入れてもらえません。傾聴力・共感力に関しては案件規模に限らず共通して必要となるスキルだと考えます。
6.今後の展望について
リーパス
今後の展望についてぜひお聞かせください。
濱谷さん
個人としては、現状の得意分野や規模に限らず、新たな分野、業種、規模の案件にも積極的にチャレンジしていきたいと考えています。また、経営コンサルにおけるPM経験をさらに増やしていくことで、さらに広い視点からコンサルに関わっていきたいと考えています。ジェネラリストとしての能力を高めたい一方で、最近はAI分野にも夢中なので、もっとこの辺りの分野も深く極めていきたいですね。
リーパスとしては、これまで中小企業診断士はもちろん他士業の業界がなかなか関わってこれなかった中堅企業領域へのコンサルにも進出し、いわゆるこの業界におけるパラダイムシフトを起こし、業界全体を盛り上げていきたいと考えています。
7.中小企業診断士として活躍していきたい方に向けたメッセージ
リーパス
最後に、中小企業診断士として今後活躍していきたい方に向けたメッセージをお願いします。
濱谷さん
リーパスでは会員登録が無料の上、比較的小規模な案件から大規模な案件まで、そして業務も業種も多岐に渡ってお仕事が紹介されています。
また、診断士をはじめとした士業やコンサル向けの動画や記事といった学べるコンテンツも豊富にあり、会員同士で意見・情報交換できるコミュニティもあるので、コンサルとして稼いでいきたいと考える人はもちろん、コンサルとしての知識やスキルを向上させたい方や繋がりを広げたい方にもぜひオススメです。
講師:

濱谷洸旭

記事
現役診断士が解説!中小企業診断士の独立は失敗しやすいのか?
中小企業診断士でLeaPath初期メンバーの山田です。
今回は、「現役診断士が解説!中小企業診断士の独立は失敗しやすいのか?」と題してお送りします。
私は中小企業診断士に登録したその年に独立をしました。それまでは中堅企業でのサラリーマンとして20年以上生活してきましたが、違う世界に足を踏み入れたことになります。
今回は自らの経験に加え、周りの現役診断士数名のお話を総合しながら、はたして独立すると失敗してしまうものなのかを検証してみたいと思います。
結論:中小企業診断士の独立は決して失敗しやすくない
結論から申しますと、「中小企業診断士の独立は失敗しやすいのか?」という問いに対しては「NO」と回答します。
私もここまで順調に進めてきていることもありますが、周囲を見回しても、診断士での独立が失敗しやすいという事例や悩みは聞いたことがありません。
それぞれ生きてきた環境の違いや経験値の差、また独立後の生活についての解釈の違いがあるとは思いますが、私が知る限りの解釈で以下深掘りしていきましょう。
独立診断士としての「生き方」
皆さんもご存じのとおり、中小企業診断士の活躍の場は独立だけではなく、企業内診断士、公的機関勤務、金融機関勤務、コンサルティング会社勤務など、様々なタイプがあります。各自の強みや志向に合わせて、柔軟なキャリア選択が可能な点も中小企業診断士の魅力と言えますね。
独立診断士の数と傾向
中小企業診断協会のアンケートによりますと、診断協会の会員診断士の約48%が独立診断士との情報があり、その割合は増加傾向にあると聞きます。
選択肢
回答数
構成比(%)
中小企業診断士として独立している
904
47.8
2年以内に独立したい
140
7.4
5年以内に独立したい
161
8.5
10年以内に独立したい
142
7.5
予定はない
515
27.2
無回答
30
1.6
回答数計
1,892
100.0
(出典:企業診断ニュース別冊 2023年2月)
中小企業診断士の年齢のボリュームゾーンは50代、60代、40代となっており、ある程度経験を積んだベテランであることが垣間見えますが、最近では30代の若手独立も増加しており、IT、Webマーケティングなど、新分野での活躍も目立ちます。
独立診断士の年収
コンサルティング業務日数の合計が100日以上(つまりほぼプロコン)の方にとったアンケートがあります。
選択肢
回答数
構成比(%)
300万円以内
83
14.3
301~400万円
51
8.8
401~500万円
58
10.0
501~800万円
124
21.4
801~1000万円
66
11.4
1001~1500万円
89
15.4
1501~2000万円
39
6.7
2001~2500万円
25
4.3
2501~3000万円
16
2.8
3001万円以上
28
4.8
合計
579
100.0
(出典:企業診断ニュース別冊 2023年2月)
独立診断士の年収は個人差が大きいことは否めず、経験や専門性によって変動します。
一般的には、初年度から3年目は300万円〜500万円、4年目以降は500万円〜800万円、ベテランになると800万円以上というイメージが多いのではないでしょうか?(筆者調べ)。
トップクラスでは2000万円を超える例も多くあり、また期間としても開業から数年で2000万円など到達される方もいらっしゃいます。
独立中小企業診断士の実例
独立診断士の実例として、たとえば、私の知っている独立診断士の方では以下のような方々がいらっしゃいます。
① 製造業出身の50代男性。生産性向上のコンサルティングを得意としている。前職の経験を活かし、現場改善で高い評価。補助金業務にも関わり、年収900万円以上。
② IT業界に転職した30代女性。創業支援やDX支援に注力。自らもプレイヤーに近い立ち位置で深く入り込み、多忙な様子。年収650万円程度か。
③ 元銀行員の50代男性。事業再生と財務改善が強み。地域金融機関との太いパイプを活用。年収1300万円程度か。
④ 元コンサルの30代男性。DX特化。専門知識で差別化を図る。「時給1万円」と自己評価。年収2000万円程度か。
⑤ 製造業出身の40代男性。10社以上の顧問を引き受け、日本全国を飛び回っている。継続的な支援を得意としており、クライアントとの信頼関係構築が上手い。年収1500万円程度か。
中小企業診断士の独立が失敗する原因
なにをもって独立の成功、失敗とするかは人それぞれだとは思いますが、ここでは、失敗の定義を
「売上(収益)が本人が想定した目標値に届かない」という風に定義させていただきます。
その前提で、中小企業診断士の独立が失敗する大きな原因として3つあると考えています。
中小企業診断士の独立が失敗する大きな原因
①独立コンセプトがあいまい
②情報が入ってこない
③経営者へのリスペクトが足りない
①独立コンセプトがあいまい
まず1つ目が「独立コンセプトが曖昧である」ということ。
言い換えると、「なぜ自分が独立したいのかはっきりしない」ということです。
「今の職場環境が嫌だから」「なんとなく自分を変えてみたい」といった内向きの理由であれば、たとえそれがきっかけであったとしても、その先に何もなければ長続きしにくいです。
解決策としては、まず自己分析を徹底的に行い、自身の強み、情熱、市場ニーズを明確にしましょう。
そして、それらを組み合わせた具体的な独立ビジョンを策定します。
「誰に、何を、どのように提供するか」を明確にし、その価値提案が市場で通用するか検証します。
明確な目的意識と独自の価値提案があれば、困難に直面しても粘り強く活動を継続できます。
②情報が入ってこない
独立が失敗する要因として2つ目は「情報不足(情報入ってこないこと)」です。
情報不足は、市場動向の把握や新規顧客獲得の障害となり得ます。
この問題を解決するには、積極的なネットワーキングが必要ですから、診断士の会合やセミナーやイベントへの出席を通じて、同業者や潜在顧客とのつながりを広げましょう。
人との繋がりでしか得られない貴重な情報というのはたくさんありますので、情報源を多様化し、常にアンテナを張ることで、ビジネスチャンスを逃さず、競争力を維持できます。
③経営者へのリスペクトが足りない
そして最後に診断士の独立の失敗原因として「経営者へのリスペクト不足」が挙げられます。
過去にこんな事例がありました。
ある製造業の会社の社長さんへ企業診断と課題解決の提案に入った際に、私としては現状の組織体制に大きな改善余地があると思い、組織体制を大きくガラッと変える改善提案を行いました。
結果としては、社長には刺さらず、社長としては一言、
社長
「もうそんなことはとっくに考えてるから、こんなプレゼン続けるんだったら寝るで。」
ということでした。
私は当時、自信満々で社長に提案資料を持って行ったつもりでしたが、このように結果としては全く思うようにはいきませんでした。
これは、私としては社長が考えて行ってきたこと(組織体制の検討を含めて)に対してリスペクトが足りなかったわけです。
社長のやってきたことの意図、今の現状に対する社長の考えに対するリスペクトを持って、ヒアリングから提案に至るまで臨んでいたらまた結果は変わったことでしょう。
以前、私が信頼する診断士の方にこう教えていただきました。
「相手の考えを否定することは非常に気を払うべきことであり、正論を言うことが必ずしも社長にとって良い提案になるわけではない」
この考えは私自身とても大切にしている考え方です。
このように、経営者へのリスペクト不足は、信頼関係の構築を困難にし、コンサルティングの効果を低下させます。
リスペクト不足の状態では、どんなに良い提案であったとしても基本的に社長の心には刺さってくれません。
まずは経営者の立場に立って考える習慣を身につけ、経営者が直面している課題や重圧を理解し、共感する姿勢が重要です。
これに加えて、助言を行う際も、一方的な助言ではなく、対話を通じて解決策を共に見出す姿勢が大切です。
経営者の成功事例を学び、その努力と決断力を評価する視点を養うことで、より深い信頼関係を築き、効果的な経営診断が可能になります。
これさえできれば診断士の独立は失敗しない
中小企業診断士が独立するにあたって、「これはやっておいたほうが良い」と思われる要素をいくつかご紹介したいと思います。
中小企業診断士の独立でやっていきたい要素
①差別化戦略の構築
②ネットワーキングとパートナーシップ
③継続的な自己投資と学習
④多様な収入源の確保
①差別化戦略の構築
診断士として成功するには、自身の「強み」を明確にする、これが最も重要ではないかと考えます。
中小企業診断士の世界では、他の診断士と差別化することが不可欠です。
特定の業界や分野に特化したり、独自の診断技術を磨いたりすることで、クライアントに選ばれる理由を作り出せれば最高です。
そこまで尖りきらなくても、自身の経験や専門知識を活かし、ニッチな市場でクライアントに見つけていただくことも手です。差別化することによって、高単価での受注や継続的な顧客獲得が可能になります。
例えば私の場合、マスコミ業界、メディア関係の診断は強みとできます。また、決算書を深く読み込めますので、社長のお話と併せて現状をつぶさに把握できます。そして、会社の目指す目標、あるべき姿を共有することで、より社長に寄り添う診断と助言に結びつけることができます。
②ネットワーキングとパートナーシップ
独立診断士にとって、ネットワークの構築も大変重要かと考えます。特に同業者同士の関係づくりに積極的に取り組みましょう。
経験上、中小企業診断士は他の士業に比べて同業同士の接点やコミュニケーションがより深いと考えています。
セミナーや交流会への参加や共同プロジェクトの実施などを通じて、信頼関係を築いていけると良いでしょう。また、自身の「弱み」が分かっている人ならば、補完できるパートナーを見つけて協力関係を構築することで、より幅広い案件に対応できるようになります。
私の場合、養成課程で知り合った同志や先輩、先生方との定期的な触れ合いを通じて、知り合いの知り合い、といった拡げ方でネットワークを築こうとしています。
③継続的な自己投資と学習
中小企業診断士は5年毎に登録更新をする必要があり、継続的な学習が求められています。
最新の経営理論やテクノロジーのトレンドを常に把握し、自身のスキルを磨き続けることが重要です。セミナーや研修への参加や情報交換の場への出席など、様々な方法で知識を更新しましょう。また、実際の案件を通じて得た経験を体系化し、自身の知見として蓄積していくことも大切です。
私の場合、大阪府診断協会や大阪診断士会で開催されるセミナーや研修にはなるべく参加するようにしています。その他の機関で開催されているセミナーも多くチェックしています。同じテーマでも講師によって議論の運び方や結論が異なることもままあります。
④多様な収入源の確保
独立診断士の安定した経営には、できるだけ複数の収入源を確保することが重要です。
経営診断業務だけでなく、セミナー講師、執筆活動など、様々な形で収益を得る方法を模索しましょう。
そのためには自らの「稼働率」をどのように割り振るかという考え方も重要になってきます。
アウトプットとインプットの時間配分なども熟慮せねばならないポイントです。特定の案件や顧客に依存しすぎるリスクを軽減し、安定した収入を確保できるようになれば最高ですね。異なる収入源を持つことは市場の変化にも柔軟に対応できるようになるなど好循環を生み出してくれると思います。
私の場合は、「実業を伴う診断士」を目指していますので、1週間(5日)を大きく2つに割り、週2日程度は診断士としての業務、週2日は実業に就く日、残りの1日はインプットを中心に活用する日として大きく分けて考えます。曜日で分けても、お客様の都合などに左右されますので厳密には難しいですが、頭の中の稼働率イメージを持っていると、仕事が詰んだり重複したりせず、柔軟に対応できます。
中小企業診断士で独立を考えている全ての方へ
独立することへの不安や迷い
独立するということは、ある組織からの離脱を意味します。その怖さは独立を志した方でないと分からないと思います。
これまでの会社や事務所が自分と合わない、とすっきりした気持ちを持たれている方もいらっしゃるかと思いますが、そうであっても一抹の不安は残るものです。それは社会との接点をその組織を通じて行ってきたからであって、そのタガがはずれると、本当に社会人の一員でいられるのか、その点が不安になるからだと思います。
でもきっと大丈夫。独立する人は皆その経験を越えて、立派に社会にアクセスできるようになっておられます。
収入の不安定さと資金管理
独立するにあたっては、私は最低2年分の生活できる資金を貯蓄しておくべきと考えます。
つまり、仕事がゼロの状態が2年続いたとしても生きていけるという余裕が欲しいということです。リミットが少ないほど気持ちに焦りが出てきます。
1年目はとにかく挑戦。そこからさらに1シーズンチャレンジできると思えば、気持ちの好循環が生まれ、事業展開も正のスパイラルに向いていくものと考えます。
おわりに
色々話してきましたが、一言で言えば、これまでのキャリアの棚卸を行い、専門領域の方向性を決め、学びやネットワーク構築を怠らず、紹介いただいた仕事を金額の多寡にこだわらず一所懸命にこなしていけば、必ず道は拓けるということに尽きます。
これらは何も中小企業診断士の独立だけに当てはまるものではありません。逆に言えば、中小企業診断士だけが独立に失敗しやすいという理由はどこにもないということになります。謙虚に、真摯に、感謝を忘れず日々進んでいきましょう!
講師:

山田和年

記事
リーパスプロジェクトインタビュー Vol.2:新人事制度の構築・導入支援 中原賢二
1.自己紹介
リーパス
本日はリーパス会員の中小企業診断士である中原賢二さんにインタビューさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。では早速ですが、まずは簡単に自己紹介をお願いいたします。
中原さん
中小企業診断士の中原賢二です。よろしくお願いします。
私は大手食品メーカーで経営戦略および事業戦略を担当する管理職として従事していますが、副業の許可を得て、個人事業主として診断士活動をおこなっています。
関東と関西では異なる活動をしています。
関東では、行政や公的機関からの受託事業や地域金融機関との中小企業M&AおよびPMI支援を通じて、国の中小企業支援施策を推進する専門家として中小企業振興に取り組んでいます。
一方、関西では、中小企業の持続的成長や経営力・企業価値の向上を支援する経営コンサルタントとして活動し、人的資本経営に関するセミナーの講師も務めています。
2.リーパスに登録しようと思ったきっかけについて
リーパス
リーパスに登録しようと思われたきっかけは何ですか?
中原さん
「診断士として新しい景色が見たい」という思いがあります。
私は大阪で養成課程を修了し、中小企業診断士になりました。同期生たちと共に学んだ際、私たちは「診断士になるため」に学んでいたのではなく、「診断士として何をすべきか」を学ぶことに重点を置いていました。
中小企業診断士の認知度は決して高くありません。その理由は、「中小企業診断士のあるべき姿」が明確に認知されていないからだと考えています。
「社会や企業に必要とされる中小企業診断士でありたい。診断士として新しい景色を創りたい」と考えるようになったのが、リーパスに登録しようと思ったきっかけです。
3.リーパスで参画したプロジェクトについて
リーパス
リーパスで参画されたプロジェクトについて教えてください。
中原さん
新人事制度の構築・導入を支援するプロジェクトです。
このプロジェクトでは、目標管理制度、等級制度、適正配置、賃金制度といった人事制度を2年かけて段階的に導入し、経営者が望む「経営の型」を創り出します。
4.リーパスでのプロジェクトの感想
リーパス
リーパスでのプロジェクトのご感想についてお願いします。
中原さん
新たな人事制度を導入するにあたり、全社員に対して説明会を開催し、個別面談も行いました。
これらの説明会や面談を通じて、社員の期待や将来への不安、さらには社員の家族との生活についても理解することができました。
リーパスでのプロジェクトを通じて、多くの社員の人生に影響を与える責任を実感し、社員の家族も含めた幸せの一助となる機会を得ることができたと思います。この理解が社長に伝わり、人事制度を定着させるまで支援する長期的なリピート契約につながったと考えています。
5.リーパスでのプロジェクトで、必要なスキルについて
リーパス
今回のリーパスでのプロジェクトで、必要なスキルはどんなスキルでしたか?
中原さん
私が必要だと感じるのは「傾聴力」「洞察力」「構造力」です。
お客様の頭の中や心の中にある考えや想いを引き出すためには、傾聴力が欠かせません。コンサルタントが一方的に話すのではなく、お客様の考えや想いを可視化し、言語化することが大事なスタートです。
次に、お客様の課題の本質が何であるかを特定するためには、洞察力が必要です。お客様自身が課題の本質に気づいていないことも多くあります。
その後、可視化・言語化した考えや思いを、あるべき姿に向けたプランとして具体化するためには、構造力が求められます。
コンサルタントの本質は、お客様が望む姿を見抜き、ゴールへのスキームを立体的に構築することにあると私は考えています。この立体的なスキームのクオリティが、お客様のニーズを満たし、報酬を得る基準になると考えています。
6.今後の展望について
リーパス
今後の展望についてぜひお聞かせください。
中原さん
私は企業で果たすべき責務があるため、当面は現在の領域で活動を続けます。
企業内診断士と独立診断士の違いは、お客様には関係ありませんから、企業での経験・診断士の経験を蓄積し、それらを財産として独立のタイミングを待ちたいと考えています。
独立後は、中堅企業、または中堅企業を目指す中小企業の伴走支援をおこないたいと思います。
その時まで、関東では行政や公的機関、金融機関とのネットワークと信頼関係を築き、関西では経営コンサルタント・講師の実践を重ねていきます。
7.中小企業診断士として活躍していきたい方に向けたメッセージ
リーパス
最後に、中小企業診断士として今後活躍していきたい方に向けたメッセージをお願いします。
中原さん
診断士の新しい景色を一緒に創り、診断士の価値を高めていきましょう。
私は「診断士は経営のプロフェッショナル」として広く認知されなければならないと考えています。
リーパスに登録している皆さんと共に、経営のプロフェッショナルとしての歩みを楽しみにしています。
講師:

中原賢二

記事
リーパスプロジェクトインタビュー Vol1:大規模成長投資補助金支援プロジェクト 山田和年
1.自己紹介
リーパス
本日はリーパス会員の中小企業診断士である山田和年さんにインタビューさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。では早速ですが、まずは簡単に自己紹介をお願いいたします。
山田さん
はい、よろしくお願いします。
山田和年と申します。私自身、過去に関西の放送局で26年勤務してきた経歴がありますが、その間、経営戦略、財務、労務などの管理業務部門に長く携わる一方、 編成や制作といった放送局ならではの業務も経験しました。番組プロデューサーとして10年以上チームの先頭に立ち、「見えないものづくり」を一丸で行ってきました。
現在は中小企業診断士として、各種補助金に関わる業務や、企業再生に関する業務を手がけています。簿記、会計について明るく、決算書を確認しながら企業に寄り添うのが得意です。
2.リーパスに登録しようと思ったきっかけについて
リーパス
リーパスに登録しようと思われたきっかけは何ですか?
山田さん
「リーパス」が、中小企業診断士を名実共に引き上げる崇高な理念を持っていたからです。
中小企業診断士は他の士業と比べて、各々の専門領域が多彩で幅広いと感じます。だからこそ、診断士が単独で課題に向き合うよりも、タッグを組んでチームで実務することにより、幅広い企業支援、社会貢献ができると感じています。
その中で「リーパス」は、中小企業側にも診断士側にもプラスになるような理念と、実際の仕組みが設けられていると感じたので登録しました。
3.リーパスで参画したプロジェクトについて
リーパス
リーパスで参画されたプロジェクトについて教えてください。
山田さん
「中堅・中小大規模成長投資補助金」の支援業務です。
この補助金は、中堅・中小企業が持続的な賃上げを目的に、省力化等による労働生産性の向上と事業規模の拡大を図るための投資に対して補助を行うもので、規模的には大きなものでした。私はプロジェクトリーダーのもと、プロジェクトメンバーの一人として参画しました。事務局への各種問い合わせや、事業戦略の検討を行うための資料作りを行い、ローカルベンチマークなどの必要資料を用意しました。
4.リーパスでのプロジェクトの感想
リーパス
リーパスでのプロジェクトのご感想についてお願いします。
山田さん
一人ではできない仕事でした。まさに「リーパス」の意義を感じられたプロジェクトだったと思います。
数十億単位の事業計画に夢やロマンを感じ、その計画が現実のものとなる姿をイメージして気持ちも昂りました。具体的な業務進行としても、プロジェクトリーダーの適切な指示があったので大きな混乱なくスムーズに進められたと感じています。これまで携わったことのない種類や規模のプロジェクトでも、いざやってみるとなんとかなるもので、さらなる自信につながるものと感じています。
5.リーパスでのプロジェクトで、必要なスキルについて
リーパス
今回のリーパスでのプロジェクトで、必要なスキルはどんなスキルでしたか?
山田さん
今回の私の経験からすれば「挑戦心」と「想像力」だったのではないでしょうか。
未経験のプロジェクトでも一歩踏み込んでクライアントの力になりたいと思うチャレンジ精神はありました。また、結果を出してクライアントが喜ぶ姿をイメージすることが最後までやりきる原動力になっていたと思います。無論、携わるプロジェクトによって必要なスキルは変わってくると思いますが、「中小企業診断士として誰かを笑顔にする」ということが活動の原点ではないかと思います。
6.今後の展望について
リーパス
今後の展望についてぜひお聞かせください。
山田さん
「リーパス」の事業領域がどんどん拡がって、さまざまなチームで多くのプロジェクトが行われることを期待しています。
私もそれにできるだけ参画しながら、個人的には「実業の裏付けがある診断士」を目指しています。自ら「中小企業のオヤジ」になることで、経営支援業務にも一層深みが増し、共感していただける度合いが濃くなると考えるからです。何足の草鞋を履けるか分かりませんが、可能性があればあらゆる支援の仕事に関わっていきたいと考えています。
7.独立診断士に向けたメッセージ
リーパス
山田さんは独立診断士ですが、最後に、現在独立を考えている、または将来的に中小企業診断士として独立したいと考えている方に向けたメッセージをお願いします。
山田さん
診断士として独立する際には、自分の「色」を出せるかが重要になるでしょう。
しかし「経験」がなければその「色」を出しにくいのも事実です。そこで堂々巡りをしてしまいがちですが、「リーパス」はその風穴を開けてくれる素晴らしい存在になると感じます。独立診断士の皆様は、時に「リーパス」に助けられ、時に「リーパス」を助けながら、一人の診断士としても成長できるようになれば良いなと思います。一人として同じ診断士はいません。だから楽しい世界です、共に進みましょう。
講師:

山田和年

動画
中小企業診断士・経営者のための 中小建設業の課題整理
このコンテンツは動画ではなくテキスト資料販売です
①建設業における外部環境を多面的に情報整理
②中小建設業の課題を3つの視点で分類し、企業の成長段階に合わせた取組み課題を明示
③自社独自の業務プロセス完成後に、競争優位性構築のために取り組む施策の方向性を明示
③診断士にとっては建設コンサルを行う上で、経営者にとっては自社の経営課題を検討する上で役に立つ建設業に関わる人のためのベーシックな資料
講師:

池田 隆
購入金額:
¥0

動画
社員のエンゲージメントを高めるために、一から始める「多様性とその受容(D&I)取組み」
「この会社で働きたい」と社員が思う理由は1つだけです!D&Iは、多様性を尊重し、全ての人々が平等に参加し、尊重される環境を作り出す取組みです。D&I取組みにより、社員のエンゲージメントを高めることができます。「企業が社員に選ばれる理由・企業が持続的に成長する原動力」の考え方・取組み方を丁寧にお話し、明日からでもできるD&I取組みを紹介します。
講師:

中原賢二
購入金額:
¥1,000

動画
「資産」とは何か?=もう一歩踏み込みたくなる財務諸表シリーズ=
●会計が苦手な方にもできるだけ分かりやすく、実務者にもより興味を持っていただけるような「もう一歩踏み込みたくなる財務諸表シリーズ」です。
●今回は「資産」がテーマです。会計の中ではメジャーな言葉だと思いますが、「資産って何?」と言われたら正確に答えられますか?
●この動画では「資産」の本当の意味を理解し、改めて会社全体を見直し、強みを見出していただけるような内容です。
講師:

山田和年
購入金額:
¥500

動画
すっきり解説!令和の農業市場で中小企業診断士が求められる理由
国内の農業市場に明るい中小企業診断士が令和の農業市場について詳しく解説いたします。
日本農業は今、大きな歴史の転換点を迎えており、中小企業診断士が活躍できるフィールドが広がってきています。
もしかすると、中小企業診断士にとって最後のフロンティア市場になる可能性を秘めています。
日本農業の流れと提案内容を学び、農業市場で活躍できる中小企業診断士になりましょう!
講師:

荒木 俊
購入金額:
¥500

動画
人材管理システムの要件
人材不足は、中小企業にとって大きな問題です。そのような中、タレントマネジメントを中心とした既存の人材の能力向上、最適配置を検討することも重要になってきました。しかしながら、それらを勘と経験でやることも限界があります。本講座では人材管理システムを用いたデータドリブン人事の内容と、そのために必要な要件を詳しく説明していきます。
講師:

中川 逸斗
購入金額:
¥2,300

動画
中小企業のBI事例 -“25の画面事例”でBIイメージをアップ!-
【本講座は動画ではなくテキスト販売です】BIツールとは、企業が持つさまざまなデータを分析・見える化して、経営や業務に役立てるソフトウェアのことです。BIツールを導入する中小企業は年々増えていますが、どのようなデータを可視化すれば良いのか分からないという悩みがあると思います。本講座では、25の事例を通して、BIのイメージアップを図ることを目的としています。
講師:

中川 逸斗
購入金額:
¥1,500

動画
中小企業の管理会計の勘所-管理会計を制すれば経営が変わる!-
管理会計は適切な経営の肝です。管理会計がある会社とそうでない会社の経営戦略や財務結果には大きな差が出てくるといっても過言ではありません。本講座では管理会計の概念、構築方法、事例を学び、中小企業が実現できる管理会計のイメージを向上させます。
講師:

中川 逸斗
購入金額:
¥3,400

動画
中小企業の人事制度の作り方
中小企業においては、人事の5つの体系ごとの重要な論点を押さえることで、本格的な人事制度を作ることが可能です。そのノウハウを作り方のプロセスを、多数の人事制度導入を経験している講師が丁寧に説明します。皆さんの会社にも人事制度を導入してみましょう!また、導入はしているけれどうまくいっていない会社の方も必見です。
講師:

中川 逸斗
購入金額:
¥3,600

動画
診断士のキャリア戦略-年収5000万円を超えるための考え方-
【本講座は動画ではなくテキスト講座です】5,000万円以上稼ぐ中小企業診断士やコンサルタントは、一体どのようなことを考えて行動しているのか?1日の業務平均時間5~6時間で、年間5,000万円以上、稼ぐためのブレない考え方。を赤裸々に公開します。事前にひとつだけ問いておきます「あなたの行動は分散しすぎていませんか?ヒントはそこにあります」
講師:

中川 逸斗
購入金額:
¥0

動画
中小企業のDX戦略vol.2アウトプット編-DX戦略を作ってみよう-
Vol.1インプット編では、中小企業でも実現できるDX内容など事例を踏まえてお伝えしました。Vol.2ではVol.1での知識を活かして、DX戦略を構築する方法をお伝えします。
DX戦略というフワッとした概念を具体的に解像度を上げていく講座です。
講師:

中川 逸斗
購入金額:
¥2,500

動画
中小企業のDX戦略vol.1インプット編-DXで使える技術はこれだ!-
DXっていまいちよく分からない・・中小企業にもできる・・?など、様々な疑問・不安があると思います。DXプロジェクトを多数行ってきた経験を活かして、中小企業でのDX事例を多数ご紹介するとともに、DXで使える技術というのも、明らかにしていきます。
講師:

中川 逸斗
購入金額:
¥3,500
動画
人口減時代の経営 「人から始まる好循環」モデル
今後、労働人口が着実に減っていきます。10年後は今まで経験したことがないような労働力不足の時代になるでしょう。ピンチはチャンスです。時代の変化を理解し、経営のやり方をスイッチすれば強い企業に進化します。
講師:

田村 俊之
購入金額:
¥0